… … …(記事全文2,211文字)
前回、東京大学大学院教授の赤川学先生の『WiLL』での連載、「13歳からの性」第10回。
男女が遠距離恋愛などで会う頻度が減れば、セックス回数が少なくなるという記述に関し、そんなことはなく、むしろ逆だという突っ込みを入れさせてもらった。
会う頻度が少なくなれば、その間に女は別の男と交わっている可能性が高くなる。
その男の精子によって妊娠する可能性も高まる。
よってそれを打ち消すため、会ったらすぐさま、何回も交わることになるはずだ。
その際、通常のセックスよりもはるかに多い精子が放出されるということが研究でわかっている、と述べた。
今回はもう1つ気になった記述、日本人の少子化は親子がいっしょに寝る、「川の字就寝」や添い寝という住宅事情、生活習慣に原因があるのではないかということについてだ。
確かに川の字で親子が寝ていると、わが子が邪魔になって親が夜の営みをいたすことが困難になる。
添い寝の習慣も同様だ。
しかしそれは単なる住宅事情、生活習慣で済まされる問題なのだろうか?
ここで考えるべきは、なぜ今いる子が添い寝をしないとなかなか寝てくれないのか、子が両親の真ん中でないと安心して寝てくれないのか、ということなのではないだろうか。
つまり、今いる子こそが無意識のうちに次の子ができる行為の邪魔をしているのではないかということだ。
こういう考えは動物行動学を学んでいると自然に出てくるものだ。
実際、40年くらい前だが、子どもの夜泣きは両親が次の子をつくる行為を邪魔するためだという論文が出ているほどだ。
なぜ子どもは次の子が生まれてくるのを阻止したがるのか。































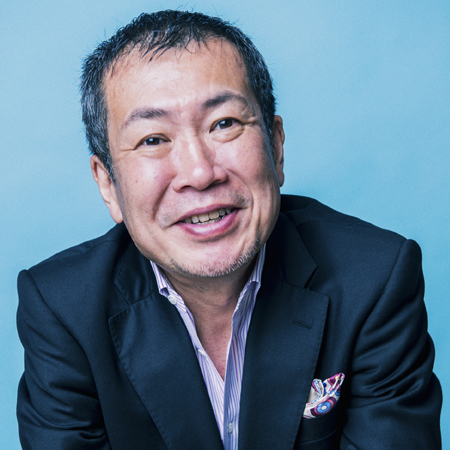













購読するとすべてのコメントが読み放題!
購読申込はこちら
購読中の方は、こちらからログイン