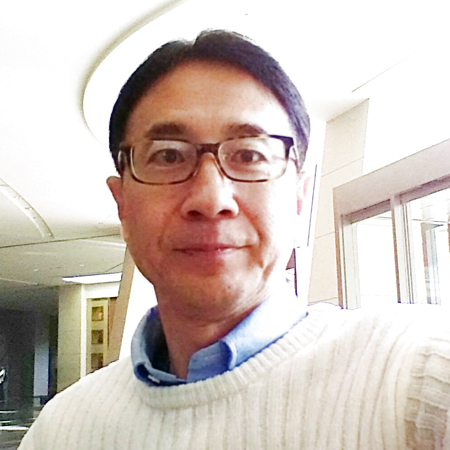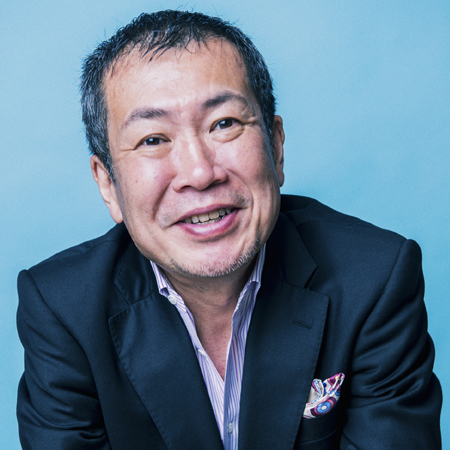■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
<1ヶ月にビジネス書5冊を超える知識価値をe-Mailで>
ビジネス知識源プレミアム(660円/月:税込)Vol.1363
<Vol.1363号:正刊:超限戦と認知戦の世界>
2023年8月23日:激動している世界のただなかで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホームページと無料版申し込み http://www.cool-knowledge.com
有料版の申込み/購読管理 https://foomii.com/mypage/
著者へのメール yoshida@cool-knowledge.com
著者:Systems Research Ltd. Consultant吉田繁治
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□現在、ヨハネスブルグで、BRICSの会議が行われいます。24日からは、1年間ドル金利と世界の通貨の予想に欠かせないジャクソンホール会議。
たぶん米国インフレと金利への、「穏やかな発言」から、
1)短期的には、ドルが上がって、
2)10月には、日銀の利上げがあるかもしれない(ドル下落)。
◎現在、約4%という大きな日米金利差があるため、円売り/ドル買いが起こって、1ドルは145.6円の高値、円は安値です。
ドルが高値なので、金は7月から12%下がっています(ドル国際卸価格、円での国内小売価格ではほぼ横ばい:1グラム9850円)。約12%ドル高/円安です。金は、ドルの反通貨(アービトラージ:代替資産)です。
ドルが上がるときは、ドル価格は下がり、ドルが下がるときは、金が上がる傾向があります。
『大転換』の400ページが一次原稿完了。約1週間をかけ、修正・削除・付加を行います。早朝から5時ころまで、あれこれを見ながら調べて、楽しく書いています。書いたものは、本当は、1か月はおいて読み直さなければならないことは知っていますが・・・
それにしても、真ん前の大工さんの建設音がカンカンと今日もうるさい。連日、もう4か月か。我慢しかない。
今日は、藤井聡太の王位戦、第5局。藤井聡太の3勝1敗。深層学習型AIの、局面評価が面白い。人間には思いつかない手を出しますが、藤井聡太の指す手と、85%くらい一致、驚異的です。いま47:53で挑戦者の佐々木6段が、ほんのわずか優勢、でもまだ54手目。あと、たぶん40手や50手はあります。
以降は、何回か書き換えた、プロローグの前半部です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<Vol.1363号:正刊:超限戦と認知戦の世界>
2023年8月23日:有料版・無料版の特別共通
【特別共有号:目次】
■■プロローグの前半部
■1.昆虫の社会の、集合知
■2.現代の戦争
■3.米国の超限戦
■4.メディアが加担する認知戦
■5.戦争禁止の国の、防衛という矛盾
■6.西側のメディア
■7.米国の、対日超限戦
■8.議会制民主主義の、発祥は英国の議会
■9.1990年代の10年は、米国が金融ローマ帝国(ドルの実効レートは95→150と1.6倍)
■11.経済と金融の基礎を決めるのは、為替レートである
■12.1993年のクリントン政権から、回転ドアが大規模にはじまった
■13.政治と産業界の、回転ドア
■14.金融ローマ帝国の反抗への影からの制裁
■15.経常収支の赤字として海外にでたドルの、米銀へのUターンのしくみ
■16.中国マネーの米国への還流
■17.人民元のドルペッグ制:1994年~2023年の29年
■18.日本の対外資産 1300兆円
■19~.海外にでたドルが、米銀にUターンするしくみ・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■プロローグの前半部
世界の経済、政治、軍事、金融、社会が80年ぶりにつぎのパラダイム、あたらしい枠組みに向かって転換しようとしている。 日本では、明治の維新、または、過去が清算された敗戦から、新世紀に向かったときに似ているだろうか。世界の枠組みが変わる時代に立ち会うのは幸運か不幸か、いずれにせよ希有(けう)である。
歴史の過去からは、現在に向かって希望あるいは悲観して歩いてくるひとびとがみえる。過去の未来は現在である。現在にいるわれわれには未来はみえない。それぞれの記憶のなかの過去と、現在の状況のなかにとじこめられている。
未来を期待して想像するのは、イマジネーションである。立方体をみたとき、裏はみえない。裏を想像することはできる。これがイマジネーションはたらきだ。未来は想像のうちにしかない。
*
未来への想像力をはたらかせるには、過去から現在までの変化の本質にあるだろう原因を探し、つまり法則や原理を探し、未来に延ばすしか方法はない。自然科学の研究の対象になる、物理的な世界は病気をふくみ、ひとびとの集合的な意思ではなく、自然の法則で動いているだろう。
他方、われわれの内的な世界は、脳の記憶、現在への認知、未来への期待である。生成型AIには、過去の記憶のまとめしかない。現在の認知と、未来への期待は人間のみが行う。いや犬や猫も、行っているだろうか。
法則には、発見されたもの、まだ発見されていないものがある。ガンの病理は、まだ発見されていない。ガンにかかったときの未来は、過去の似た症例の治療のデータを未来に延長する「推計の統計学」をつかって、確率でいうしかない。
診療した医師の、「治癒の確率が70%」が示すことは、症例の過去の多数データを未来に延長する「推計の統計学(標準偏差)」である。
株価では、過去20日の価格の変動から標準偏差をとったボラティリティと、株価の移動平均線を中心に、標準偏差の1倍、2倍、3倍の幅をもつボリンジャー・バンドが、推計の統計学である。過去と現在は、確定している。未来は、確定していないから確率になる。
「南海トラフの大地震の、30年以内の発生確率は70%」と政府の地震研がいうのも、過去の大地震が発生したサイクルを。記録がある2000年くらいならべて確率にした、推計の統計学である。単純な数式にならない複雑系である大地の地震の原理・法則はまだ発見されていない。未来は、過去の大地震がおこった頻度から、推計の統計学でいうしかない。
地球が太陽の周りを回る自然の重力の作用は、数学的にほぼ正確に発見されている。70年後の地球の位置は、正確に予想ができる。この位置に、地球がもどる確率は80%という、推計の統計学ではない。人間の寿命の80年あと、90年あと、いやこれからは100年か、の位置も決まっている(太陽系を固定した座標として、そのなかでの位置)。
超多数の要素が絡み合った、人間と人間の世界である、経済・金融・社会も、偶然でうごくのではない。まだみえてはいない原因と必然があるはずだ。それがなにかを書く過程でさぐっていく。経済、金融、株価、通貨は社会的で人間的なものである。ひとびとの、集合的な認識と判断の結果によって、価格がうごいている。
■1.昆虫の社会の、集合知の事例
ミツバチには、巣の設計者はいない。個々のミツバチは、本能で動いて、みごとな6角形の巣を作り、蜜を集める。個々のミツバチのあたまにはない「社会の集合知」がこれである。こうした、個々人をこえる集合知が、市場で売買される商品、株、証券、国債、通貨、つまり、全部の金融商品の価格である。相場がある金融商品の全部の価格は、個人が決めることはできない。
株価は過去の取引の結果であるが、市場には不特定に多数の投資家がいて、個人ではなく投資家全体の投票(株の売買)の結果、つまり集合知で決まっている。しかも価格は固定せず、時々刻々、異なって取引された結果の価格が変動する。株価はしばしば生き物に例えられるが、株価自体は、生き物ではない。近い未来の株価への、われわれの心理的な期待値が生き物であり、その期待知を作る情報の解釈と判断の仕方が、変化していく。
昨日と今日では、おなじ株価の予想値、または期待値は変化している。株価は大きく変化する。以降では、変化した戦争から述べる。しかし、ミツバチは、いつもおなじかたちの巣を作る。
戦争は、国家・経済・社会・文化まで大きく変えるものだったから。
■2.現代の戦争
社会の基礎、あるいは下部構造は、経済であろう。
新型コロナのパンデミックにつづいた、経済活動の暴力による戦いの、ウクライナ戦争を機に米国と欧州、米国の影響が強い日本は、その基礎からの、変化の時代をむかえている。
戦争は、社会とひとびとの認識を変えるから、歴史の転換になってきた。
ところが、現代の戦争は、知らないひとが多い「超限戦」になった。軍事行動だけではない。マネーと金融と株、資源・エネルギー、メディアの操作による認知戦、ハッキング、スパイ、法の制度まで、つまり社会と経済の全体をふくみ、一方の利益を目的にしたハイブリッドな混合戦争である。
超限戦の観点に立つと、日本は、米国・中国・北朝鮮から仕掛けられた宣戦布告のない戦争状態であろう。北朝鮮がミサイルを飛ばし、中国が台湾を威嚇(いかく)して軍事演習を行い、尖閣列島の領有を主張するのは、何かの自己利益を目的にした超限戦の一部である。米国は、日本の政治を操作している。
日本の政権と外務省に、超限戦への認識はあるだろうか。認識とは、たんにみること、あるいはみたことではない。理解と共通だが、言葉で描いて、他人に説明できるまで理解することである。
みたことを理解しないと、認識ではない。その理解には、感覚的・感情的なものと、理性的・客観的なものがある。感覚的、感情的なものは主観である。他人や社会には、個人の枠内にとどまる主観(私が見ている青の感覚、聴いた音楽の感覚)は、伝えることがむずかしい。
理性的な認識は、言葉や数字で、他人に伝えることができる。
これが、科学者が、実験をして事象の論理を書く論文である。
現代の経済学は数式をつかうので、一見、科学めかしてはいる。しかし、おなじ事象の、おなじ条件での実験による検証ができないので、経済学者は科学者ではない。
ひとの認識と判断で売買が行われている経済や株価の未来は、予想をしても確率的である。ひとびとの価格への認識と判断は変わっていくから。
■3.米国の超限戦
米軍と一体の活動が多いCIA(約2万人)は、米軍の諜報機関といわれる。活動の内容は、軍事戦略、スパイ、暗殺だけではなく、経済・金融・IT・情報の超限戦の、戦略企画・立案・実行の機関である。
キーワードを決め、世界中のインターネットとメールの全文を検索し、日本世界の政治・外交・産業情報を、検索・盗聴・監視しているのは、NSA(米国家保安局:3万人:ウィキ・リークスのスノーデンが職員の1人だった)であり、盗聴では、CIAと一体である。
じつはグーグルも、最初はCIAが作ったシステムであった(1998年:カリフォルニア州メロンパーク)。
その有名になった子会社が、youtubeだ。グーグルでのキーワード検索は、NSAが行っている世界の情報の全文検索とおなじものである。現在はAIがつかわれ、情報検索は自動化されている。機械が行えば、人間は、決めたキーワードにひっかかった、すくない結果を読めばいい。
領域は政治、軍事、IT、経済、研究機関、論文など多岐(たき)にわたる。日本には、こんな機関はない。ハッカーとは区分がない。
中国では、人民解放軍が、超限戦の企画・実行の機関である。北朝鮮では、中国で訓練されたハッカー6800人を擁(よう)する軍がそれである(人数は韓国国防省の推計)。国家プロジェクトであり、本当の目的があるはずだが、それはいわず、実験といって頻繁にミサイルを撃ち、日本や韓国を威嚇(いかく)している。日本への超限戦と認識しなければならない。
米軍の指令部であるペンタゴンは、2001年の9.11(同時多発テロ:ワールドトレード・センターの崩壊)から戦争をテロ戦争と定義した。テロ戦争は内容が複雑であるため、宣戦布告がされない超限戦のひとつの形態である。テロ戦争は、石油の支配権を巡り(めぐり)中東では戦後からはじまっていた。
ロシアでは、プーチンの出身母体である、ソ連のKGBの後身、FSB(ロシア連邦保安庁:35万人)が超限戦の機関である。暗殺を極端に恐(おそ)れているプーチンは、旧KGBや現FSBの出身で側近を固めている。現代の戦争は、2000年ころから、はっきりと古典的な戦闘ではなくなった。
安倍元首相は、プーチンの一行を、山口県の老舗の料亭旅館『大谷山荘』に招き会食した(2016年12月15日)。
名産のフグが出されたが、フグと日本酒に手をつけなかった。同席していたプーチンの側近が食べても平気なのをみると、プーチンも食べて美味しいといった。日本酒を飲んで旨(うま)いといって、『ご当地獺祭(だっさい)』を1箱、ロシアにもって帰るよう側近に命じた。いつもブスッとした顔で、プーチンがやることには、何かおかしさがある。
ウクライナ戦争も、米国・NATO・ウクライナ連合軍とロシアとの、軍事の戦闘だけではない。エネルギー・資源・穀物・金融システム・通貨への主権の争奪までふくむ超限戦である。バイデン政権で、ウクライナ戦争の戦略を作っているCIAの高官は、以下のように述べているという。
ソースはマスコミの倫理から匿名(とくめい)である。〔ニューズウィーク誌(23.08.01号)〕。
「ウクライナで起きていることの全部は、秘密の戦争であり、そこには秘密のルールがある。米国とロシアは長年かけて、そうした秘密のルールを作り上げてた。CIAがとてつもなく重大な役割を果たしている」
つまり、CIAとFSBが合意で作ったルールでの戦いという。戦争にはルールはない。この戦争にはルールがある。両方が破滅するエスカレーション理論の核戦争は、認知戦である。発動するとは、いう。そのつもりはない。これも「ルール」である。
ながくつづいても、何もできないわれわれは、停戦をまっていればいい。民兵のワグネル軍2万5000人を率いるブリゴジンの反乱もルールのうちのものだろうか。秋には終わるという説も米国の軍事関係者からでてきた。首脳の動きからは、停戦もみえる。
「秘密のルール」があるとすれば、この戦争にも出来レースがまじっている。主流メディアの、溢れる報道は何を報じているのか。双方に相手を悪として世論を盛り上げるためのフェイクがまじり、本当のことと見分けがつかなくなる、プロパガンダ(宣伝戦)である。
宣伝は、自分にとって有利な長所・利点・正義を強調し、不利になる短所・欠点・不道徳・犯罪はかくす。メディアが流すプロパガンダが米国と西側の世論を盛り上げないと、米国はウクライナ戦争から手をひかなければならない。マネーと兵器の支援ができなくなる。2003年のイラク戦争のとき、米国の軍事費支援のため、小泉内閣は米国債買いを30兆円も行った。今回は15億ドル(210億円)の保証をする。
世界の政府からは、国民は主流メディアに操作されるひとびとだ。民主政治では、世論の支持がないと政策と戦争は実行できない。戦争が国の正義ではなく、政府とつながる軍需産業、エネルギー、食糧メジャー、国際金融資本の利益を目的としていても・・・
■4.メディアが加担する認知戦
防衛費を、5年で2倍の43兆円にすることをはやばやと決定した日本には、米国はメディアをつかう認知戦も動員する。日本側に超限戦への知見(ちけん)があるとは思えない。
GHQは日米戦争をおこした機関として、内務省(内務官僚に岸信介がいた)を解体した。自衛隊には、防衛大学にも超限戦、IT、金融への頭脳はないだろう。
米国・中国・北朝鮮・ロシアがしかける現代の戦争の、超限戦への理解がないと、日本の将来も好ましいものにならない。当方にできることは、全力でこの本に書き、ひろく知らせることである。超限戦では、国民に事実を知らせるべきメディアも、政府が世論を喚起(かんき)するため動員するので、本当のことの認識がむずかしい。記憶にあたらしい、いや、もう古くなったか、22.7.08の安倍元首相の暗殺も、どこかの国の超限戦にみえる。
奈良県警が、1)当たった弾道からは、物理的にありえない山上単独犯としたこと、2)80m先の駐車場の壁に作られた3つの偽装にみえる弾痕、3)動機を、宗教団体への恨(うら)みとしたことの3点からあきらかである。
3つとも犯罪の構成要件としては、法の常識に照らしてムリだろう。この3つの疑問に奈良県警はいまだに答えていない。なぜか2024年に延期された裁判でもあきらかにならないだろう。なぜ、公開の裁判を、理由を述べず、1年も先に延期するのだろう。
たぶん検察は、公開される物証に困っている。裁判は公開である。
■5.戦争禁止の国の、防衛という矛盾
日本では、戦後憲法が戦争を禁じた。われわれの社会を転換させてきた戦争についての、学術研究はなく、フィクションがまじる歴史小説だけになった。戦前・戦後の、世界の戦争の歴史も、ひとびとの意識から、なくなった。軍事が国家の枠(わく)を作るという現実の政治論もなかった。
軍事とは無関係な、万世(ばんせい)一系(いっけい)とされる天皇制のなかで、戦後は、国民のたぶん80%が空想的な平和論と、現実にはムリな非武装の中立論に傾斜してきた。
政府・外務省・自衛隊・メディアには、現代の米国・中国・ロシア・北朝鮮がしかけている超限戦への認識はないようにみえる。
5年での倍増が決定した、防衛費43兆円では、米国から1970年代の時代遅れのトマホークを買うだけでなく、どこかが敵国になってもしかけてくる超限戦からの防衛手段、防衛ツールを備えた訓練をすべきである。超限戦から防衛できるよう、法も変えなければならない。米国からの輸入だけではなく、自前の武器製造も必要だろう。
国産の武器生産は、政府からの発注が安定しないため、民間会社は武器の生産ラインが維持できず壊滅的になっている(三菱重工・川崎重工・富士通・石川島播磨・三菱電機・NECが主要な6社)。対策としては、20兆円の防衛費の、予算プールを作るべきだという(日本の軍事関係者)。
21世紀の2020年代以降は、AIをそなえた武器と核兵器の、自国での生産ができない国は、独立は果たせない。武器の生産が本当の自衛である。日本人のおよそ60%が、米国依存を続けることをえらび、独立はしたくないとすれば話はべつであるが。
世界の政治と外交は、メディアを動員する「認知戦(にんちせん)」になっている。認知戦とは、ひとの脳の認知領域にはたらきかけ、判断と言動を目的にそうようコントロールすることである(苫米地英人)。慰安婦も、韓国側からの、露骨な認知戦である。
認知とは、外部現象を認識して理解することであり、理解とは、原理や原因を知ることである。主流メディア(新聞とTVのニュース解説)は認知戦の道具になっている。その自己認識は、ないだろう。メディアは、超限戦の現実をみていないどころか、すすんで認知戦の道具になりはてた。
・戦争のときのように、国民の自由な行動を政府が管理し、規制ができる国家非常事態宣言が出されたコロナパンデミック(2020年)。
・7年は必要な治験(ちけん)の期間が、6か月しかなかったワクチン(2020年)。
・原因が追及されていないウクライナ戦争の報道では、露骨(ろこつ)に、認知戦がつかわれている(2022年)。
古典的な19世紀末の『戦争論』のクラウゼヴィッツは「戦争は政治の延長だ」といった。現代では政治そのものになった。この戦争論は防衛大学の教科書として古すぎる。
認知戦では、世論の形成のため主流メディアを動員し、フェイク情報を事実にみえるようにして報じる。
各国政府からの、自国民と、仮想敵の国民への世論操作も、認知戦である。
■6.西側のメディア
CNN、ワシントンポスト、NYタイムズ、ロイター、そして、日本の共同通信の報道記事を、論の隠れた根拠までテキストを仔細に読むと、根っこにある事実が、180%、ねじ曲がっているものがまじっているものが多い。大学でやったが、「テキストの構造主義的分析」で分かる。
現代の大手メディアの、フェイクをいうテキストの根拠は、相手の論に根拠がない、あるいは陰謀論とするものである。しかし、陰謀論とされたことの多くは、事実をしらべていくと、一般に入手ができる状況証拠からは、ホンモノの陰謀にみえた。
人間は動物とちがって、言葉ではウソをいえる。証言は、自分を不利にする自白であっても、物的な証拠がないかぎりは、真実ではないこともある。自爆テロとおなじ構造のものだ。
ひとは、自己と自己の利益を守ると前提して、自白が信用できるものになる。乗客として飛行機にのるとき、われわれが見知らぬパイロットを信用して命をあずけるのも、パイロットは自爆をしないと信用した上でのことである。
タクシーの利用、レストランでの食事でもおなじだ。見知らぬ他人が調理するレストランでも、毒がはいっているとは疑わない。社会は、お互いを信じることで成立している。しかし、プーチンは信用せず疑う。
つい最近、マウイ島で、原因が疑わしい山火事がおこった。突然に広がった火に閉じ込められたかも知れない1000人以上が今も行方不明という。普通、木が燃えてゆっくり広がるしかない山火事は、1000人が逃げ遅れて、火にとじこめられるようなものか。
迫ってくる火から逃げる1分が、なぜなかったのか。普通はありえないことが、近年、相当な頻度でおこっている。
フェイクを真実とする超限戦のなかの認知戦は、われわれの社会の、お互いを信じるという前提を壊す。とりわけ、2020年11月の米大統領選以来のメディア報道、怪しい新型コロナ・ウィルスとワクチン、ルールがあるというウクライナ戦争も、認知戦である。
米国で11月ころから、強力に変異したコロナが、再び猛威を振るうという情報もあるが、これは本当か? 個人ではおこせない犯罪の多くには、組織が、誰かを有利にする目的の陰謀がからんでいると、判断していいだろう。
■7.米国の、対日超限戦
米国は、ペンタゴンとCIAの役割を、国土と国民の防衛だけではなく、経済・金融・社会の領域までの、総合的な安全保障を図(はか)ることとしている。
人民元・ユーロ・円と、米ドルの立場からの、金融戦争のシミュレーションは、CIAの秘密委員会でコンピュータ・プログラムを作り、ジェームス・リカーズが主要メンバーになって、金融技術の専門家も参加して行っていた(著書の『ドル消滅』がこれを書いている)
日本に仕掛けられた、経済面の認知戦、つまり超限戦をいえば、
1)1985年の、プラザ合意(ドルの1/2への切り下げ、日本は外貨で50%の損をした)、
2)世界へのプレゼンスが現在の中国の銀行のように巨大になったが、自己資本比率が4%台とすくなかった日本の銀行への、1988年からのBIS規制の強化(リスク資産に対する8%の自己資本の要求。世界1だった、日本の銀行の押さえ込みが、目的だった:日本の銀行は融資を縮小→資産バブル崩壊、不良債券200兆円。
3)1970年代から繰り返されてきた、対米輸出規制(日本の輸出の抑圧(よくあつ))、
4)1986年からの半導体摩擦(世界シェアが50%だった日本の半導体の生産潰しだった。現在はわずか8%に減った)、
5)1990年からの、公共投資の1年40兆円と、対米輸出を減らす内需の拡大を求めた構造協議。
対米輸出の抑圧:90年年代の10年で、400兆円の国債発行を行って公共投資を実行。拡大予算が欲しい官僚は、喜んで応じた。利用価値が低く、経済を成長させる乗数効果のない、無駄な公共設備が日本中にあふれ、1200兆円の現在の国債残と、GDPゼロ成長の起点になった=二度目の日米敗戦がこれである。
6)米軍スタッフと日本の官僚が、現在のエマニュエル駐日大使のもとで会合をもち、国の方向を決める重要な政策・法案作る日米合同委員会(米国の目的は日本経済の弱体化、ドル買いの要請。米国からの、兵器の輸入の促進)。
いずれも、米国からの超限戦の経済戦争としての、対日の認知戦だった。
■8.議会制民主主義の、発祥は英国の議会
現代につながる議会が成立したのは、英国だった(1801年)。国内の封建諸侯(貴族)が、領土をめぐり、繰り返していた内戦を、議会での論戦に変えることが目的だった。つまり、議会は議員のディベートでの認知戦と、立法による超限戦の場であった。
米国の、民主党と共和党の対立は南北戦争が、現代風に形を変えた超限戦である。中国の台湾と、尖閣列島の領有の主張も、超限戦である。
米国の対日戦略は、通貨が変動相場に移行した1973年から、50年一貫して、米国をこえる恐れもあった、ドイツと日本の産業とマネー力をおさえつけることであった。
2000年代は、対中国に重心が移った。米国の経済、金融の安全保障のために、ドイツと日本の政治を従属させた。
政府、日銀、銀行に米国債の買いを要請してきたことは、ドル戦略である。
CIAは、超限戦での侵略をする対象国に、エージェント(代理人、代理機関)を作って、個人名と組織をあきらかにせず潜伏(せんぷく)させる。ウクライナには約100人のCIA職員が存在し、現地のエージェントは、数が知れない。ゼレンスキーも、CIAからお金をもらうエージェントといわれるが、たぶん事実と考える。
中国は、日本・米国・欧州に対して、多数のスパイとエージェントを、官僚組織、政党、メディア、大学、有名会社、金融に潜伏させている。現在の日本には留学生、官僚、メディア、IT、自衛隊、大手の会社勤務者をふくみ、5万人の、中国からのお金で動いている工作員がいるという。あなたの近くにも、普通のひとにみえる工作員がいることは確実である。
対米国では、数が知れない。対日が5万人なら、3倍の15万人か。14億人の中国は、何ごともスケールが大きい。
産業に基幹的なITや金融だけでなく、米国の軍事情報、兵器産業、政治に入りこんでいる。北朝鮮ですらハッカー6800人だから、中国のハッカーやスパイはその何十倍も多いだろう。ロシアの秘密警察のFSBが35万人だから、その2倍の70万人か。
安倍元首相暗殺や、岸田首相パイプ爆弾くらいのスケールの小さいことなら、どこかは不明だが、お手のものだろう。駐留米軍と一体のCIAは、日本の政治の監視をふくむ、公然のスパイ活動ができる。菅内閣が内閣ブレーンに採用したデービッド・アトキンソンは、たぶんその幹部だろう。
超限戦、認知戦、金融戦争の観点では、米国は、日本を友好国とは、みなしていない。
たぶん、英国だけが、金融・経済・軍事・情報での米国民主党の友好国であろう。米国の共和党は、民主党とおよそ逆なので、日本にとっては、トランプへの好悪はべつとして、共和党がいいだろう。
ドイツも、米国の超限戦の対象であることが、ウクライナ戦争の過程でロシアからドイツへの、バルト海底にある天然ガスのパイプライン、ノルドストリ-ムの、偽装的な爆破であきらかになった。米国は、目的達成のためなら、何でもやる。
社会とは、共通の言語、文化、価値観の集合体であるが、表と裏がある。
経済とは、マネーを媒介にした商品の生産と売買であるが、これにも表と裏がある。
経済とマネーは、1991年に、ソ連と共産主義が崩壊したポスト冷戦のなかで、グローバル化されてきた。マネーの面では、地球の全地域が、冷戦のあとの民主党クリントン政権(1993-2001)のころからドル金融になってきた。
■9.1990年代の10年は、米国が金融ローマ帝国(ドルの実効レートは95→150と1.6倍)
冷戦後の1990年代の米国は、欧州、産油国、中国、ロシア、日本を従え、海外にでたドルをUターンさせる、基軸通貨のしくみをもつ「金融ローマ帝国」になっていた。
1990年代に、ナスダック株が、価格の加重平均の指数で455(1990年)から2000年の4810まで10年で10.6倍に上がったことも、当時は富裕国だった日本を先頭に、旧共産圏をメンバーに加えた世界からのマネーが、ドル買い・ドル株買いに走ったからである。
米国は、海外からの借金(=ドル買いは米国への貸付金)で、経済を成立させている。
経常収支の構造的な赤字から、自然なら下がっていくドルの実効レートは、90年の100から、2000年は120まで上昇した。実効レートとは、世界の貿易量で加重(かじゅう)平均(へいきん)した通貨レートの指数である。
経常収支が構造的な赤字であり、約50年、ドルを海外に垂れ流しているドルは、外為市場の自然からは、下がるべき通貨である。
対外負債の多いドルの実効レートが上がることは、
1)基軸通貨とされているドルの、世界の銀行の買いが、
2)米国の金融面の超限戦によって、売りより多くなっているという外為市場の事実を示す。
米国は、戦略的な国家である。独立戦争(1775-83年)のあとの245年に100回、2年半に1回、大小の戦争をしてきた。常時戦争国だから、ハイブリッドな超限戦も「平和な」日本をふくむ世界にしかけてきた。
■11.経済と金融の基礎を決めるのは、為替レートである
実効レートが下がる通貨は、外為市場で売りが多い通貨である。上がる通貨は逆である。
通貨のレート変動は、外為市場での、通貨の売買額の変動とみなければならない。
外為市場は、株式取引所のような一カ所ではない。世界の銀行の通信、ネットワークのなかにある外為銀行の店頭(てんとう)である。
日本人がドルに交換するときは、国内の外為銀行で、円を売りドルを買って交換する。日本の大手銀行は外貨を売買する外為市場のひとつである。銀行間送金のSWIFT手順の通信が、相互に結ばれているから、銀行の店頭が外為市場になっている。
銀行では、外貨や国債も買うことができ、外銀の口座への送金もできる。仮想通貨でも売買と海外、自国への送金ができるスマホのインターネットをイメージすればいい。
米国は、
1)ドルが円では240円から120円へと、1/2に下がった1980年代、
2)下がったドルが、逆に上がった90年代も、経常収支が赤字を続けている。
ドルが上がるファンダメンタルズ(基礎的な経済条件)は、1980年代からの米国にはない。
たとえば、世界最大の株価の時価総額(3兆ドル:420兆円:23年6月)のアップルのスマホやPCの生産は中華圏(中国、香港、台湾)であり、米国にとっては輸入になる。
アップルの時価総額(企業価値)は、東証の全銘柄3899社の、時価総額820兆円の半分であり、トヨタ(40兆円)の10.5倍である。アップルの株価時価総額は、人口6733万人の英国経済のGDP(430兆円)に等しい。これは、正常な株価か。
バブルではないとしている市場は、オランダで実際にあった、17世紀中期のチューリップバブル幻想のなかにいて、これが正常と考えている。最高価格は、家一軒分だった。どんな根拠からも、この価格は合理的ではない。
経常収支が赤字を続ける米国の通貨ドルは、外為市場の自然では、変動相場制になった1973年から、続けて、下がらなければならなかった。
では・・・990年代からのドルは、なぜ、外為市場の自然に反して、上がったのか?
海外からの、赤字のドルの買いが多かったからだ。なぜ、下がるべき赤字の通貨ドルの、海外からの買いが、売りより多くなっていたのか。
変動相場の、ドル基軸通貨の、SWIFTシステムは、
1)米国経収支の赤字として海外にでたドルを、
2)FRBと米銀にUターンさせている、200か国の銀行を巻き込むものだが目にはみえないしくみなので、少しながい物語が必要である。
SWIFT(国際銀行間の通信協会手順)は、200カ国の銀行が加盟する送金回線。全世界を覆うインターネットのような、物理的な専用回線である。
ウクラナ戦争のとき、米国はロシアへの制裁(せいさい)として、ルーブルをSWIFT排除し、ロシアの約20兆円の外貨準備(50%)も凍結した。
ロシアはエネルギーの西側への公式の輸出ができなくなって、世界の原油価格は約2倍に高騰した。ロシアは中国の送金網のCPISをつかって、中国とインドに、1バーレル60ドルという約1/2の価格で輸出した。このため、中国とインドにはインフレがない。
■12.1993年のクリントン政権から、
回転ドアが大規模にはじまった
クリントン政権には、金融のゴールドマン・サックスから「回転ドア」で来た財務長官ルービンのドルを上げる超限戦があった。回転ドアは、産業と金融のマネーと行政権力でつながった政府・官僚と、IT、エネルギー、軍需産業、金融、製薬、大学をふくむ、天下りと天上がりのシステムである。
これがあるかぎり、米国は倫理的な国ではなく、対外超限戦と戦争国家である。断言ができる。
「回転ドア」は、米国の利益と、世界の利益を食べて増殖(ぞうしょく)するガンである。
米国では、大統領の政党が代わると、約3000人の幹部官僚と政権のスタッフが入れ替わる(政治任官という)。政府官僚から失職したときは、民間のシンクタンクや金融業に潜伏し、帰属する政党が政権をとったとき戻ってくる。これが米国風の天下りと天上がりのしくみの回転ドアである。米国に留学し、シンクタンクに帰属していた竹中平蔵も日本向けの1員だった。総務大臣を務めた。
バイデン政権には、トランプになって下野したオバマ政権の幹部官僚の多くが、復帰している。国務長官のブリンケンと、2014年のウクライナに行き、ヤヌコビッチ大統領を倒すクーデタを指揮していたのは、現在の国務副長官のビクトリア・ヌーランドだった。
戦闘の停止を決めた「ミンスク合意(2014年)」は、プーチンをだますためのものだったと、当時の反ロシアの、ドイツ首相であり協定の文案作りの当事者だった科学者のメルケルは、述べている(2022年)。
これが、2022年からのウクライナ戦争の淵源(えんげん)になった。
■13.政治と産業界の、回転ドア
米国の政権は、自分の雇用の団体でもあるので、反対政党を執拗(しつよう)に攻撃する。陰謀論とされていたが、公式な用語になったDS(ディープステート:影の政府)は、民主党の回転ドアに潜んでいる。
クリントンからオバマとバイデン政権で露骨になった。
しかし、ほとんどのひとは回転ドアのしくみを知らない。メディアは、政府の認知戦に加担する道具なので、これを報道しない。このため、ウクライナ戦争での米国やロシアの、秘密のルールがあるという目的と展開も、わからなくなる。
この回転ドアを知らず、アメリカは世界一民主的な国家だから、日本も学ばねばならないという米国の表面しか、みていない論もある。
トランプは、2016年の大統領選挙で、事前の予想を覆(くつがえ)して勝ったあと、スタッフの人選と、メディアからの執拗(しつよう)な人身攻撃(民主党がフェイク情報でしかけた認知戦)を受け、これは一体何だと追求し、回転ドアのしくみを知った。
民主党の2024年大統領候補、ロバート・ケネディ・ジュニア(JR)は、10歳のとき叔父を、14歳のとき父を暗殺され、回転ドアを肌感覚で知っている。
■13.FRBの金との戦争は、1980年から2000年までつづいた
ドルの反通貨であり、ドルが上がると下げ、ドルが下がると上がる金は、10年で1オンス(31.1グラム)が1990年の400ドルから、2000年は270ドルに下がった。
FRBが、金の売買を許可している、少数の大手ブリオンバンク(JPモルガン、ゴールドマン・サックスが代表)に、FRBの金を2%の金利でリースし、金市場で売らせて価格を下げたからである。
目的は、1985年に米ドルを2分1に切り下げたあとも、米国に特権的な国益をもたらしているドル基軸体制を維持することである。
1990年に、異例のスピードで、国際金融資本の最大手、ゴールドマン・サックスの会長になっていたルービンは「金がドルの反通貨であること」を知っている。
1)金が、FRBがそのときの限度とする一定線以上に上がり、
2)上がった金価格と反対に、ドルが下がると、
3)米・欧・日以外の、ドルペッグ国の中央銀行からの、ドル外貨準備の売りがはじまり、
4)中央銀行ではドルの代替資産(金融用語ではアービトラージ)と見なされている金買いが自然に増え、ドルの基軸通貨のポジションがあやうくなっていく。
FRBから金のリースを受けるJPモルガンやゴールドマン・サックス(金を販売できるブリオンバンク)は、1980年以降1999年Mまでの20年、大量の先物売りで金価格を下げる市場操作を行った。
満期に下がった金を買って、清算するとき濡れ手に粟の利益がでた。FRBと、米国の5大国際銀行の利害は一致している。
約2%の金利を払って、FRBから金のリースを受けた国際金融資本は、喜んで金先物売りをして、ルービン財務長官の8年間も、金の価格を下げ続けた。
1990年代の、1)ドル高、2)金価格の下落、3)ナスダック株の高騰は、ルービン長官と財務省スタッフが動員され、世界に向かってしかけた、ドル買いの超限戦だった。
金融戦争のシミュレーションも行っていて、軍事、金融、経済、メディアへの戦略シナリオ作りが得意な上級スタッフが、少なくとも、1000人はいるCIAが計画をねったのかもしれない。クリントンやルービンの頭だけでは、企画・実行できないだろう。
■14.金融ローマ帝国の反抗への、影からの制裁
日本とドイツは、1993年のクリトン政権から明確化した米国の金融ローマ帝国化に反抗した首相や大臣は、ときおり、スキャンダルで葬ってきた(1976年ロッキード5億円事件の田中角栄、1998年米国債売りをいった橋本龍太郎、2009年日本は米国のATMではないといった中川昭一の泥酔会見。
これも、認知戦と超限戦であった。目的があるはずの、安倍元首相の暗殺と岸田首相へのパイプ爆弾は何だっただろうか)。
1)ソビエト連邦が崩壊して、ソ連圏の東欧が資本主義になり、
2)エネルギー・天然資源・穀物の国有企業を、格安で譲り受け短期間で新興資本になったオリガルヒができ、トウ小平の中国も開放経済に変わった1990年代に、日本には金融・経済での、冷戦後の戦略がかけていた。
戦略とは、作った目標・目的を達成するための、効果的な手段(戦術)の整合的な束をいう。
米国には、ソ連崩壊後のロシアと、東欧のエネルギー・天然資源・穀物を支配した、オリガルヒの買収と出資の金融戦略として、対ロシア・東欧(ウクライナへの金融侵略を含む)と、1994年からは中国のマネーへの、整合的な超限戦があった。
中国の開放経済も、「1994年からの人民元のドルペッグ制」をみると、米国(クリントン政権のルービン財務長官)が計画し、仕掛けたものかもしれないと思える面がある。
1990年代のクリントンは、ウォール街の投資銀行とともに成長する中国に利権を作っていた。
80年代までの日本の次にきた90年代の成長国の、中国の金融は1994年からの、人民元発行のドルペッグ制だった。
バイデン一家も、ウクライナのオリガルヒの、エネルギー会社から利権を得ていた。ウクライナ戦争は、バイデンにとっては、ウクライナでの不正利権隠しでもある。
米国は、1994年からの人民銀行のドルペッグ制採用とともに行われた、人民元の切り下げにより、約10分の1に安くなった中国商品を輸入し、ディスカウントストアで売った。
(人民元の長期レート;1980-2022)
https://ecodb.net/exchange/cny_jpy.html
人民元が、1980年の1/13の11.5円に下がった1994年からの日本では、ユニクロとニトリが先行して開発輸入を行い、急激に売上を増やした(平均年率の売上増加25%の30年)。国内での衣料の縫製は5%の高級品に減って、家具インテリアも1/2から1/3の価格に下がっていった。
■15.経常収支の赤字として海外にでたドルの、米銀へのUターンのしくみ
人民銀行は、1)中国の金融近代化と、2)貿易に必要な人民元とドルとの交換性を確保するため、米ドルを準備通貨としてもって、そのドルを資産に、人民元を発行している。
金融制度の改革のため、中国の開放・改革を行ったトウ小平(しょうへい)から招聘(しょうへい)された、米銀のゴールドマン・サックスが人民銀行を指導し、中国にドルペッグ制の導入を行った(1994年)。
ドルペッグ制は、ドルとの交換レートの変化幅を、中央銀行によるドル売り/ドル買いの介入によって、1年に2%から3%程度に抑え、安定した交換レートを維持する通貨制度。
人民元、香港ドル、シンガポールドル、サウジアラビア、湾岸産油国はドルペッグ制である。ドルペッグ制をとる国は、自国通貨の増加発行のとき、貿易を黒字にしてドルを買わねばならない。
このため米国が、日本、産油国、中国に対して貿易赤字を続けても、ドルが下落しない。人民元のドルペッグ制は、ドル基軸の通貨体制の維、持のために戦略的に考えられた、超限戦の金融制度である。
1960年代から90年までの30年、米国の生産経済は、衰退を続けてきた。しかし1990年代からは、逆に、マネーの面のドル金融は、旧ソ連圏の東欧、ロシアと大国の中国を巻き込んで、世界化した。
日本の円に加え、1994年からは、中国も米ドルの赤字を引き受け、
1)米国からは経常収支の赤字として流出したドルを、
2)ウォール街の銀行に還流させる役割を担う(になう)ようになった。
■16.中国マネーの米国への還流
中国の対米輸出の貿易黒字として中国に貯まるドルが、米銀への預金として、米国に還流するしくみである。
日本の資産バブルが崩壊した、1990年から1991年の冷戦終結のあと、旧共産圏に拡大して世界金融になったのが、
1)米ドルのグローバル金融であり、
2)その結果の、米国の金融ローマ帝国だった。
軍事以上に、社会の基礎を作るマネーと金融に目をつけた米国は、世界帝国として成立と崩壊のローマ史を研究していたことになる。
米国は、世界の2分の1の地域だった自由圏のドルを、1990年から世界に広げた。
これが1990年代の10年で、95年からのインターネットの世界化(WWW:ワールドワイドウェッブのしくみ:CIAが作った)と関連して、米ナスダック株が10倍にあがった原因である。
冷戦終結後の米国は、世界金融帝国になり、事業利益の20%が金融利益になった。
しかし1999年には、10年準備したドイツのコール首相の主導で、欧州統一通貨ユーロが作られ、米国と合計の人口とGDPがおなじだった19カ国がドル圏から抜けた。
ドル基軸通貨圏の縮小が原因になって、世界からはドル売りがおこって、ドルは本書で示す実効レート130(00年)から、100(07年)にまで23%下がった(図は5章:5-3)。
https://honkawa2.sakura.ne.jp/5072.html
米国の株価は、ドルの下落や上昇より先行する。日本株とは逆に、米国株はドル高(海外からのドル買いの超過)のとき上がり、ドル安(ドル売りの超過)のとき、下がる性質がある。
ナスダック株は、00年4月の高値の5000から、02年には4分の1の価格に暴落した。その後、2001年は、世界同時多発テロ(9.11 WTCの怪しい崩壊)と、2003年はCIA1がでっち上げたフセインの大量破壊兵器というフェイク情報による「正義」の、イラクへの侵略だった。
■17.人民元のドルペッグ制:1994年~2023年の29年
人民元のドルペッグ制は、1994年からだった。1990年代の通貨戦争を企画したCIAと、財務長官のルービンをヘッドとした実行部隊のFRBとが組んだ、米銀からの認知戦だったので、一般の目には「人民元のドルペッグ(Peg:ひっかけるが原義)」の意味がわかないから、通貨戦争としては目立たない、しかしスケールが巨大な超限戦であった。
意図を隠した大きすぎる動きは、しばしばひとに見えなくなる。「そんなバカな」と否定するから。
人民元の交換レートを、為替介入によってドルに連動させるドルペッグは、人民銀行のバランスシート(B/S)をみれば、明白である。
B/Sを単純化すると、
「人民銀行の資産=米銀へドル預金約4兆ドル:負債=人民元の発行30兆元(現在は20円;600兆円に相当)」である。
1ドルは現在7.5元付近であるから、ドル預金と人民元の発行額は等しい。これが、ドルペッグ制である。中国の貿易黒字(米国の対中国の貿易赤字)が、中国からの米銀のドル預金として、FRBと米銀に還流するこのしくみは、1994年に作られた。
人民元の通貨発行額(マネタリー・ベース)は、「中国の対米黒字=米国の貿易赤字分」だった。
なお20年後の2010年ころからは、今度は逆に、中国からの米国・欧州・日本への超限戦が仕掛けられ、現在に至っている。
日本は、1980年からの、経常収支の黒字の40年分(平均30兆円/年)に相当するドルを、対外資産として買って、米銀へのドル預金・ドル国債・ドル債券として、赤字のドル覇権をささえるだけだった(40年の累積が対外資産1338兆円:2023年5月末:財務省)。
■18.日本の対外資産 1300兆円
対外資産が、40年も一度も減ったことがなく増え続けたことは、日本から米国への驚異的な忠誠を示す。日本人は、自分の上に立つものに、忠誠を尽くす伝統と国民性をもつ。
底に武士道が残っているのか。武士道は主君と決めたものへの、命までを捧げる忠誠の倫理(りんり)だった。マネーの献金なら、命よりは軽い。国家を運営する政治家と高級官僚にとって、米政府は主君だった。本当の主君は、国民でなければならない。
憲法の字面(じづら)では、国民主権と書かれている。実態はちがう。主権とは、国家を統治する行政の権力である。国家は、経済の単位である政府+企業+世帯の、三つの主体で構成されている。
経済面ではGDP(国内総生産の金額)だが、GDPの中身は「企業(及び医師や農業などの個人事業)の所得+世帯の所得+機械と設備の減価償却費」である。
GDPが伸びることは、減価償却費は過去の設備投資からの一定なので、企業所得+世帯所得が、伸びることにほかならない。
■19~.海外にでたドルが、米銀にUターンするしくみ・・・
ページ数が超過するので、今回はここまで。現代の世界の金融、経済、社会、国家戦略を見るときの前提になることを、最初に書いています。これが、プロローグの前段です・・・メディアや一部学者の論のフェイクの根幹も、これで、原因が100%わかります。
超限戦で、右に左に歪められてきた日本は、改革・修正しなければならない。当方にできるの、本を書いて広く知らせ、認知を変えることです。1980年代までの、もう忘れられたかもしれない日本とドイツには、米国も超える素地が、確かにあったのです。米国が抑えてきました。今後の対策は、超限戦を知ることが第一段階です。第二段階は政治と官僚改革・・・第三段階が、産業対策。
【ビジネス知識源プレミアム・アンケート:感想は自由な内容で。 以下は、項目の目処です。】
1.内容は、興味がもてますか?
2.理解は進みましたか?
3.疑問点はありますか?
4.その他、感想、希望テーマ等
5.差し支えない範囲であなたの横顔情報 があると、今後のテーマと記述の際、より的確に書くための参考になります。
コピーして、メールに貼りつけ記入の上、気軽に送信して下さい。
感想やご意見は、励みと参考になり、うれしく読んでいます。
時間の関係で、返事や回答ができないときも全部を読みます。
時には繰り返し読みます。【著者へのひとことメールおよび読者アンケートの送信先】
yoshida@cool-knowledge.com本ウェブマガジンに対するご意見、ご感想は、このメールアドレス宛てにお送りください。
配信記事は、マイページから閲覧、再送することができます。
マイページ:https://foomii.com/mypage/
【ディスクレーマー】
ウェブマガジンは法律上の著作物であり、著作権法によって保護されています。
本著作物を無断で使用すること(複写、複製、転載、再販売など)は法律上禁じられています。
■ サービスの利用方法や購読料の請求に関するお問い合わせはこちら
https://letter.foomii.com/forms/contact/
■ よくあるご質問(ヘルプ)
https://foomii.com/information/help
■ 配信停止はこちらから:https://foomii.com/mypage/