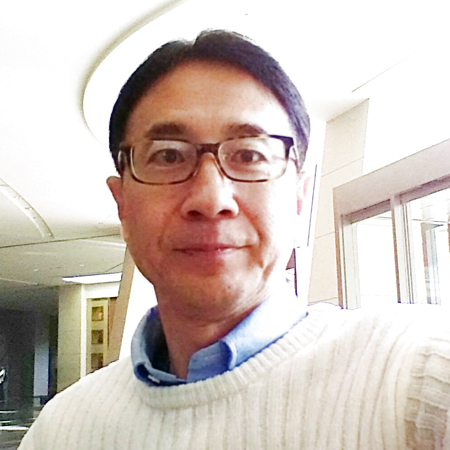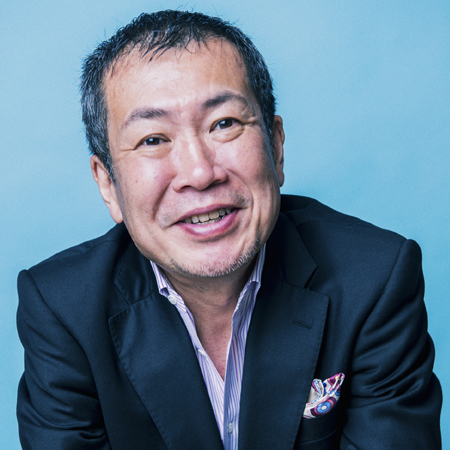■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
<1ヶ月にビジネス書5冊を超える知識価値をe-Mailで>
ビジネス知識源プレミアム(660円/月:税込)Vol.1366
<Vol.1366号:金価格の構造変化とデジタル通貨>
2023年9月13日:通貨の大転換に向かっている世界
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホームページと無料版申し込み http://www.cool-knowledge.com
有料版の申込み/購読管理 https://foomii.com/mypage/
著者へのメール yoshida@cool-knowledge.com
著者:Systems Research Ltd. Consultant吉田繁治
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
9月も半ばになり、穏やかな気温になってきました。8月は126年で最高の平均気温だったという(27.48度:気象庁)。2位は1994年の26.72度でした。
金価格は1グラム1万円(小売価格、消費税込み)を超えました。主因は1ドル146円付近の円安です。1Kgのゴールドバーが1009万円あたりですから確かに高い。しかしこの1万円に重要な意味はありません。
明治15年には1グラムが1円で、1ドルでした。140年で1万倍です(年率平均6.8%上昇)。毎年1kgずつ買い増していくと、140Kgで14億円です。円が140年で1万分の1に下がったのです。こうした金買いは、今後も正しい方法です。通貨は増えても、金の生産は増えないからです。スイスには100年スパンでマネー運用を考えるひとたちがいますが、日本では少ないでしょう。せいぜい1世代の30年か。原因は、歴史を長期で見ないからでしょう。
◎見逃してはならないのは、金の需要に、今後5年続くとも見える「構造変化」が、23年6月から起こっていることです。
需要の構造変化、つまり新興国の中央銀銀行による「ドル離れ=金買いの増加」が金価格を上げ始めたのが2023年です。
【金証券の売買の動因】
2006年から2022年までの16年間の金価格は、「ドル実質金利の変化」が原因の、西側の諸国からの売買の大きさで、決まっていました。
ところが2023年は、ドルの実質金利には無関係な「新興国の中央銀行の金現物買い」がはいってきて上げたのです(2023年6月以降)。これは、少なくとも5年は続く変化になるでしょう。10年先はわからない。
金の現物市場は、1)17世紀からのロンドン(ロコ・ロンドン:ロスチャイルド)と、2)スイスです。世界で1年に生産された4600トンくらいの金の地金(じがね)はロンドンとスイスに集まって売買され、価格が決まっています(Fixing;その日の値決め)。
2010年ころから増えたNYのCOMEXは、米欧の金融機関とファンドによる「金先物の証券市場」です。
日本からの、金の売買への参加は極めて少ない。円は、金の値決めには無関係です。日本からの金地金の買い越しは、1年に10トンから20トンくらいしかない。
中華圏(中国、香港、台湾)がもっとも多く800トンから1000トン、インドが400トンから700トンくらい。中東が200トンから300トン、北米が200トンくらい、欧州が300トン台です。
【国際卸価格と国内価格】
金は、3つの市場で、ドルで売買され、1オンスの国際価格が決まります(1925ドル付近:9月初旬)。
◎日本国内の小売価格は、そのときのドル/円のレート(147.4円:9月7日)で換算され、小売りマージン(0.5%から0.7%)と消費税の10%が加わって、1グラム単位の円価格になっています(1万0069円:9月7日)。国内で売るときも、消費税がかかった価格です。
「国際卸価格(1925ドル)÷31.1グラム×円レート(147.4円)×1.1≒円での金価格(1万0069円)」です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<Vol.1366号:金価格の構造変化とデジタル通貨>
2023年9月13日:有料版・無料版共通特別号
【目次】
■1.ドルの実質金利が決めてきた金価格
■2.金の売買に現れた、世界金融の構造変化
■3.構造的な買いの原因
■4.売られるドルの買いを、一手に引き受けているのが日本
■5.今後の、日銀の金利
■6.ロシアとサウジが決めるようになった原油価格
■7.2022年末からの、新興国の現物金の買い集め
■8.新興国の中央銀行が金を買い集めている理由
■9.通貨リセット=デジタル通貨への切り替えの時期
■10.政府紙幣デジタル通貨の世界
■11.三菱UFJとみずほが共同でデジタル通貨を発行(2024年)
【後記】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1.ドルの実質金利が決めてきた金価格
◎最近16年間の金価格は、「米ドルの10年債の実質金利」に反比例する傾向が強かった。ドルの実質金利が低いときはドルレートが下がり、金は上がる傾向があります。
この実質金利は「名目金利-ブレークイーブン・インフレ率(=インフレ連動債の金利)」で計ります。
1)米10年債の実質金利が上がる時期は、金利がない金が売られてドル債が買われ、金価格は、下げる傾向がありました。
2)逆に、米10年債の実質金利が下がるときは、金が買われてドル債が売られて、金価格は上がる傾向があったのです。
(米国10年債の実質金利と、金価格:PICET:04年~23.08)
https://www.pictet.co.jp/investment-information/fund-insight/fund-watch/gold/Gold-20230831.html
ドルの10年債の実質金利は、23年8月現在、「10年債の名目金利(約4%)-米国の期待物価上昇率(約2%)」です。(米国10年債の実質金利:現在約+2%:9月7日)
(米国、名目金利と実質金利の推移:18.01-23.08)
https://stock-marketdata.com/reai-interest-rate-us.html
◎10年債の実質金利(TIPSという)は、
・10年債の、額面に対する名目金利から、
・市場の投資家集合の、10年間の物価予想である期待物価上昇率を引いたものです。
この実質金利は、
・金融緩和の時期には、マイナスの金利になり、
・引き締めの時期には、プラスの金利になります。
・経済に中立的な実質金利は、金利=期待物価上昇率であり、0%です。中立とは、経済の引き締めでも緩和でもない金利です。
1)コロナ期の2年前の2021年8月は、マイナス1%であり金融緩和でした。
↓
2)FRBが米国インフレに対応して、利上げをしてきた2023年8月は、プラス2%であり、急激な金融引き締めになっています。実質金利0%が、景気に中立的な金利です。金価格は下がるはずです。
以下のグラフで、2018年1月から、23年8月までの、10年債の実質金利と、金価格の動きを対照しています。
(10year US TIPs Yield and Gold Price)
https://thegoldobserver.substack.com/p/the-west-is-losing-control-over-the
【実質金利と、1オンスの金価格/ドルの関係】
1)18年1月~19年1月の1年間
実質金利 +0.5%→+1.0% 金価格1350ドル→1280ドル
◎実質金利利が0.5%上がって、金価格は70ドル下がった。
2)19年1月~20年6月の1年5か月
実質金利 +1.0%→-1.0% 金価格1280ドル→1900ドル
◎実質金利が、-2%の幅と大きく下がったから、金価格は1年5か月で620ドル(+48%)と大きく上がった
3)20年6月~23年5月の3か月
実質金利 -1.0%→-0.5% 金価格1900ドル→1800ドル
◎FRBのインフレ対応の利上げで、実質金利は-1.0%から-0.5%へと0.5ポイント上がったので、金価格は、100ドル下がった
4)23年6月~23年8月・・・この時期に異変が起こりました。
実質金利 -0.5%→+1.5% 金価格 1800ドル→1900ドル
◎米国のインフレ率が低下して、実質金利は-0.5%から+1.5%へと2ポイントも上がったのですが、下がるべき金価格は、逆に100ドル上がった。普通は金が20%くらいは低下するはずです。ところ金価格は上がった(=金現物の買いが増えた)。
↓
◎2023年6月から、ドル10年債の実質金利と金価格には、過去のトレンドとは違った、逆の動きが見えようになったのです。
〔23年6月から8月の異変〕
2023年6月からは、ドルの10年債の実質金利が上がっても、過去は下がっていた金価格が上がるという、逆の傾向になっています。
↓
ドル債券と金の現物市場の、買い手/売り手の構造が変わったことを示すのです。
なお金先物の出来高は、1日に150トン(1.5兆円)、1週で750トン(7.5兆円)くらいはあります(先物の売買単位は1Kg≒1000万円)。150トンの売買で、上がるときも下がるときも金価格を先導しています。証拠金に対するレバレッジは10倍くらいが平均でしょうか。値動きの10倍の損益が出るということです。
具体的には、金1KGの価格が清算の限月に1100万円に上がったときは、先物買いは100万円の利益、先物売りは100万の損です。レバレッジが10倍で証拠金が100万円なら利益率100%、または損失が100%です。ヘッジファンドの大口投資が、先物をやっています。もちろん個人でも、金投資の口座を開くと行えます。
■2.金の売買に現れた、世界金融の構造変化
大口金融投資家とファンドは、国債、債券(社債や証券化商品)、株式、通貨、金や原油などの金融商品に、割合を決めて分散所有したポートフォリオで、短期売買をしています。
時間的には、長期保有が50%、短期売買も50%くらいでしょう。こうしたポートフォリオ売買が、市場の70%から80%を占めていることを、個人投資家は知っておかねばならない。
◎ファンドは、証券の組み合わせと、時間ポートフォリオでリスクヘッジをした投資をします。
総利回りは5%から10%/年程度に下がる。しかし他方で、相場が下がったときの損はポートフォリオ(分散投資)でヘッジしているから少ない。
ファンドは、投資家からの預託金を運用し、損が生じると解約が増えて破産(消滅)するので、損を計上してはらないのです。利益率を上げるより、損をしない運用をします。
◎大口投資家は、ドルの10年債の実質金利が上がる局面では、
・国債と債券価格の利回りも上がるので(価格は下がる)、
・国債と債券の保有の、平均金利を上げる目的で、
・ドルの実質金利が上がると、売りが増える国債・債券を買い増すことが多い。
一方で、ドルの10年債の実質金利が上がる局面では、金利のつかない金は、売られることが多かったのです。
◎国債と債券の実質金利が上がる局面では、金先物や金ETFが売られて、短期の金価格は下がることが多かった。
ファンドでは、移動と保管が必要な、現物の売買は少ない。売買するのは先物証券と金ETFです。
【3つの金市場は裁定取引で、価格は一致する】
金現物、先物、金ETFの売買市場はそれぞれが別です。市場間では、価格にわずかな差異が出ます。
↓
このときは証券会社やファンドが「高い方を売って、低い方を買う裁定取引(確実な利益がある)」を、リアルタイムの取引所の価格ボートと超高速回線を引いて、鵜の目・鷹の目で狙っているので、価格差が出た瞬間に裁定取引がはいって、短時間で一致していきます。
金証券の売買は、主に、西側のファンドと金融機関で行われています。
◎西側市場での金証券(金の先物証券と金ETF)の売買で、
1)米国10年債の実質金利が上がるときは、金価格が下がり、
2)実質金利が下がる時期には、金価格が上がる、という強い傾向があったのです。
〔23年6月からの異変〕ところが、2023年6月からは、米国の期待インフレ率の低下から、10年債の実質金利が-0.5%から+1.5%まで2.0ポイントも上がったのに、普通なら下がる金価格が上がっています(1800ドル→1900ドル)。
2か月で2%も実質金利が上がると、普通なら1800ドルの金価格は1500ドルへと17%は下がっていたかもしれない。その想定価格に比べると、400ドル(22%)上がったのです。
これは、金市場の異常な変化です。
■3.構造的な買いの原因
◎現在、普通ではないことが金市場に起こっています。
答えを言えば、中国、インド、ロシア、トルコ、中東など中央銀行の「ドル国債売り=金現物買い」です。
西側諸国(G7)の、金の売買の論理は、
1)ドルの実質金利が下がるときは、債券を売って金を買う、
2)ドルの実質金利が上がるときは、債券を買って金を売ることです。
これが、2023年6月からは、ドルの実質金利には無関係な、新興国の金現物買い(ロンドンとスイス市場)によって、構造変化を起こしたのです。金地金を買ったのは、いずれも、BRICSデジタル通貨連合(R5)への加盟予定の中央銀行です。
1)新興国の準備通貨であるドル国債、ユーロ国債、ドル預金が売れて、
2)金買いに振り替わっていることが、2023年6月から明らかになりました。
【ドルだけが、なぜ上がっているのか】
この時期に、米ドルが上がっているのは、金利差が約4%と大きな円で、ドルが買われているからです。
↓
たぶん、月間で10兆円規模の円売り/ドル買いの超過ため、ドル・円のレートは147円の、「超円安」の水準になっています。
◎ドルを買い支えているのは日本です。もっとも大きくドルを買ってきた中国はドル買いからはずれ、逆に、ドル国債を売っています。
(注)ただし、9月からは、世界でもっとも低い円金利上昇の傾向です(長期金利0.655%)。これは、若干の円高へ振れることを示しています。
■4.売られるドルの買いを、一手に引き受けているのが日本
【日本の金利限界】
日銀は、米国より高くなったエネルギーと生鮮を除くコアコア物価4%(8月:速報)のインフレに対応して、金利が2%上がると、1200兆円の国債価格が15%下がって、「銀行危機→財政危機」になるため、金利を上げることができない(日本の金利上限は1%付近)。
【一カ国だけ低金利の、日本】
円の、人為的な低金利(=日銀の国債指し値買い)のため、ドル金利との差が4%にもなって、日銀当座預金に増えた円が売られてドルが買われ、147円の円安になっているのです(9月8日)。
【ドルとの金利差が4%=普通の時期の、2%の2倍】
米国のインフレが3%台で長引くと、金利差からの円売り/ドル買いが続くでしょう。
◎主要国でただ1カ国、3%から4%台のインフレの中で、利上をせず、短期0%、長期金利0.6%の金融緩和をしているのが日銀です。(注)米ドルの長期金利は4.29%に上がっています(23年9月6日)。日米の金利差は3.7%と大きい。これが、円売り/ドル買いを促進しているのです。これは9月末に向かって円の金利が上がると、「ドル安/円高」に向かうことも示します。
1ドル146.8円は、過剰な円安です。日米の4%に近い大きな金利差が2%台に縮小すれば、1ドル=120円台(2021年の水準)でしょう。日銀はFRBから、中国が抜けたドル買いを要請されているのかも知れません。日銀は、事実上はFRBの日本支店です。
■5.今後の、日銀の金利
日銀のいまの低金利は、2023年末、2024年とつづけることはできない。コアコア物価のCPIが4%と、米国(3.2%:7月)より高くなったからです。(総務省:CPI:2022年から23.08)
https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/kubu.pdf
コアコア物価4%が続くと、円の金利は最低でも2%でなければならない。遅くとも、10月までに、円の利上げがあると見ています(0.25%か?)。そうなれば、ドル安/円高です。
【ロシアと産油国が、資源・エネルギー価格を支配する】
◎サウジとロシアの減産(100万バーレル/日)によって、原油が70ドル(23年07月)から、9月初旬は86.5ドルに上がっています(24%)。
原油価格の上昇は、資源価格全体と電力の24%付近の上昇も示します。23年秋に向かって、原油が下がったため、下がってきた物価が、再び上がることになります。
◎原油価格は、物価に、約3か月は先行する指標です。
(原油価格:1年で見てください)
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/data/clc1.html
原油価格の、1バーレル85ドル台への高騰から、金融市場が期待している「2023年のFRBの利下げ」はなくなり、ドルの利下げは2024年3月以降にずれ込むでしょう。米国が、原油価格のコントロールの手段を失ったからです。
■6.ロシアとサウジが決めるようになった原油価格
◎世界の、景気を決めるエネルギーと資源生産は、ウクライナ戦争からは、米国の中東地域への影響(米国覇権)がなくなって、産油国の連合とロシアのプーチンに、牛耳(ぎゅうじ)られています。ウクライナ戦争は、米国にとって「藪蛇(やぶへび)」だったのです。
◎西側のインフレと金利は、原油の生産調整ができるロシア、サウジが決めることになった。ロシア・サウジが生産を抑制すれば、原油・資源価格が上がってインフレになり、金利も上がります。
【ドル覇権の後退】
原油と資源の流通へのドル覇権は失われ、今後、回復する見込みがない。1973年以来、50年ぶりの革命的な変化です。
世界の原油需要は、1日1億バーレルですが、これは急に減らすことができない。備蓄は、3か月分くらいに減っているでしょう。
このため、ロシア・サウジが100万バーレル(需要の1%)でも生産を抑制すると、原油価格は20%や30%も上がります。
【天然ガスの生産】
ロシア(699bcm/日)、イラン(244bcm/日)、カタール(170bcm/日)の生産が多く、世界の発電の37%に使われている天然ガスが生産の抑制で、3倍から5倍に急騰するのは、ガスは気体であり備蓄ができないからです(LNGは液体です)。
bcmは、天然ガスの日量生産を表す単位であり、1単位が100万立方メートルです。ロシアは、2022年には天然ガスを12%減産しました。このため、欧州では、2020年に対して5倍、10倍に上がって、米欧日の物価上昇の主因になったのです(2022年7月)。
(注)日本の発電は、天然ガス37%、石炭32%、石油6.8%、水力7.8%、再生可能エネルギー10.3%(太陽光6.7%、バイオ2.6%、風力0.7%、地熱0.3%)です。
あちこちで目立つ風力発電は0.7%でしかない(2019年)。原子力発電は20%を占めていましたが、2011年の3.11の、フクシマの事故以来ゼロになり、現在は6%です。
ここも「あともどりのない構造変化」です。エネルギーと資源供給にも、重大な構造変化があります。
◎ウクライナ戦争のあとのロシアと産油国の連合は、西側の物価と金利をコントロールできるようになったのです。
(注)2023年9月から10月には、円安を避けるため、さすがの日銀も利上げをするかもしれない。そのときは、ドル/円は、下がります(円は上がる)。
■7.2022年末からの、新興国の現物金の買い集め
金の現物市場でもっと大きなロンドンのロコ・ロンドンでは、2021年までは、1年に600トンくらい金が流入してしました(輸入超過)。
◎ところが、2022年2月末にウクライナ戦争が始まって、ロシアが、金ペッグのルーブルのデジタル通貨発行を発表したあとの2022年からは、ロコ・ロンドンで買われた金が、海外に流出するように構造変化が起こりました。
原因は、ロシア、中国、産油国の中央銀行の、金買い集めです。
1年にほぼ400トンのペースです。
https://seekingalpha.com/article/4631273-the-west-is-losing-control-over-the-gold-price
スイス市場でもロンドンとおなじ、「金の流出(輸出)」が起こっています。1年に600トンペースです。
金ETFは、2022年は300トンのペースで売り越されて、金価格下落原因になりましたが、2023年6月以降は、売り越しは停止しています。(金ETFの増加と減少)
https://seekingalpha.com/article/4631273-the-west-is-losing-control-over-the-gold-price
・金の現物を買っているのはアジア(中国、インド、東南アジア)と中東の産油国、トルコ、ロシアです。
・売っているのは、米欧と生産国のアフリカです。
https://seekingalpha.com/article/4631273-the-west-is-losing-control-over-the-gold-price
■8.新興国の中央銀行が金を買い集めている理由
ウクライナで戦争は、戦闘だけでなく、
1)エネルギー・資源の支配戦争、
2)マネー覇権の戦争を含む超限戦です。
戦争を期に、通貨連合を組んだBRICSと産油国は、中国、ロシア、サウジを中心にして、
・貿易通貨をドルから、
・各国のデジタル通貨(R5)に変えていく計画を推進しています。
◎原油・資源・商品の貿易に、現在の決済通貨のドルを使わず、デジタル通貨にすることです。
BRICSと産油国は、従来のドルペッグから、金・コモディティペッグのデジタル通貨にすることを表明しています。金・コモディティの価格指数とデジタル通貨が連動する仕組みです。
◎エネギーと資源・穀物の輸出国にとっては、輸出価格が上がって収入が増える通貨の上昇は、歓迎すべきことです。
世界の需要が一定しているエネルギー、資源、穀物の輸出は、価格が上がっても減らず、輸出国の利益が増えるからです。そして、米欧日から輸入価格は下がって利点が出ます。通貨の上昇は2重のメリットがあるのです。
【時期は5年か?】
このため、BRICSと産油国は、たぶんこれから5年をかけて、金現物を、ロンドン、スイス市場から買い集めて価格を上げる。これが、2023年6月に始まったのでしょう。
一挙に、現在の外貨準備のドルを売って、金を買うこともできるのですが、それでは損をします。
ドルが急落して金が急騰するからです。金が急騰すれば、買い集めは、難しくなっていき、急騰の分、そのあとの下落リスクも高まります。
ここから、金を集める量は、たぶん年間1000トンと推計します(最大1200トン)。800トンから1200トンという意味での、±20%の幅のある1000トンです。
◎1000トンのリサイクル精製を含んでも、世界の生産量は4300トンから4600トン/年くらいしかない。買われた金現物が市場に出ることはほとんどありません。
金の現物は、長期に秘匿される金属だからでしょう。1000トンの金価格は、現在価格では10兆円ですから、新興国の中央銀行の、合計の金買いとしては、小さなものです。
【2024年からの金価格の上昇ペース】
◎中国、ロシア、産油国を先頭にして、新興国の中央銀行が、1年間に1000トン買い越した場合、金価格は、年30%から40%は上がっていくでしょう。
5年で1.3の5乗=3.7倍から、1.4の5乗=5.4倍の金価格です。ドルでは、3.7倍で7030ドル、5.4倍で1万2600ドルです。
【米国の金ETFの売り】
ドル支持の米FRBと国際銀行資本(その運用部門がファンド)が、必死に、金ETFを売っても、現物買いの1000トンには勝ちません。この価格は、FRBと国際銀行資本からの、金ETFの売りを想定したものです。
もし金ETFが売られないなら、5年での金価格の上昇は、この2倍の7.4倍から10.8倍になっていくでしょう。
(注)ただし、本稿ではこれはないものとします。なお金ETFの発行高は、3791トンしかありません。600トン売って6年分です。
中央銀行は、通貨価値を下げるので長期保有の金現物は売りません。売るのは、短期保有の金ETFです。金先物の売りは、期限日には買いもどすので、1年では売り越し(純売り)になりません。
(2022年:WGC;World Gold Council)。
ドル・円が145円付近のままなら、1グラムで3万7000円から、5万4000円です。5年後のドルは1ドル70円を想定しているので、その半分の1万8500円から2万7000円でしょうか(現在は1万円)。
【5年で1/2のドル安になると・・・】
日銀が、インフレでも金利を上げず、1ドル145円のままなら、1グラム3万7000円から5万4000円です。1ドル70円になると、日本世界でのGDPは2倍のシェア10%にもどり、賃金は米国並みに上がって、今は負けている韓国の2倍に回復します。
100%が海外輸入のユニクロの衣料や二トリの家具インテリは半分の価格になるでしょう。カロリーの60%を輸入している食品の店頭価格も、30%は下がるでしょう。3倍や4倍に上がったいくらや、2倍に上がった輸入肉も安くなる。海外旅行も半分に下がります。これが、1ドル70円の結果です。高くなった寿司屋も下がります。
政府は、1ドル146円の円安が「物価高の主因」とは言いません。なぜでしょう。コアコア物価4%上昇のインフレの中で、利上げをしない日銀が、物価高の原因だとなるからでしょう。
これから3年でなくたぶん5年で、
・ドルは1/2に向かって下がり、
・金は、ドル価格で3.7倍から5.4倍、
・円価格では1.8倍から2.7倍に上がっていくと予想しています。日本の4%の、コアコア物価上昇率は、円高になれば、3か月遅れて下がっていきます。
今回の、金現物の需要の構造変化は、貿易通貨部分の金ペッグ通貨のデジタル化(R5)への移行を示すので、長期化します。
日米欧と、BRICS、産油国、グローバルサウスの主要国の、政府の計画では、世界の通貨のデジタル化は、決定しているからです。時期だけが未定です。(2025年からか?)。
■9.通貨リセット=デジタル通貨への切り替えの時期
◎デジタル化(銀行券から政府通貨)への切り替えは、現在、金利の上昇から深いところで進行している、日・米・欧の、同時銀行危機から財政危機の発現と、ときを同じくするでしょう。
「中央銀行+銀行」が、政府の財政赤字から発行される国債を買っています。
◎銀行危機(つまり銀行の信用の縮小)は、日・米・欧の構造的な財政赤字の政府が発行する国債の買い増しの不能を示し、政府の財政危機(マネー不足)になっていきます。銀行の信用とは、信用乗数での通貨の発行能力、貸付金の増加能力を示します。
銀行の自己資本が、総資産(仮に100兆円)の10%の不良債権(仮に10兆円)の増加によってなくなったときは、信用創造能力がなくなります。
国民が、自己資本をなくした銀行からは、預金引き出しの危機を感じて預金を引き出し、銀行は資金不足になって、国債や債券を買うこと、貸付金を増やす銀行活動が実行できなくなるからです。
逆に、1ポイントの金利の上昇つき、価格が7%は下がる国債と債券を売って、預金引き出しの現金に備える。その売りで、銀行は損を、一層拡大し、倒産会社のように、資産ゼロにまで資産縮小していくしか方法がなくなるのです。
ここが、日・米・欧の財政に、国債の増加発行の余裕があった2008年のリーマン危機と違う点です。
↓
リーマン危機のときは、日・米・欧の政府が国債を発行し、中央銀行がそれを買って4兆ドルのマネーを銀行システムに供給して、金利は0%に抑え、銀行の資産縮小の信用危機をおさめたることができたのです。
◎今回は、当方の試算では、金融危機に対して、日米欧で20兆ドル(2800兆円)マネーの増発が必要です。この金額は、日銀、FRB、ECBの中央銀行の、信用創造力の限界を超えています。
中央銀行が、信用創造の限界を超えて通貨を増加発行するとどうなるか? インフレ率が2年くらいで10%→15%→20%→40%・・・と上がっていき、現在のトルコ(物価上昇40%、金利25%)のようになっていきます。
↓
◎以上を防止するには、過去の、中央銀行の銀行券を廃止して、財務省が発行する政府紙幣であるデジタル通貨に交換するしか手段がない。これが、通貨リセットです。
■10.政府紙幣デジタル通貨の世界
銀行券が政府紙幣に、1:1で切り替わると、政府の負債(金利のついた借用証券)である国債も、政府紙幣(現金)なりますから、国債という概念がなくなって、現金になります。
これは、経済にインフレをもたらしますが、中央銀行の銀行券と国債のデジタル通貨への交換を、1年間ずつ、適正量に制限することによって、流通する現金を、政府が調整してインフレを防ぐことができます。(注)100%を即時交換したら、ハイパーインフレです。
デジタル通貨の取引所になっていく銀行に預けて、退蔵されるデジタル通貨には、何%は不明ですが、政府からの利子補給として預金金利がつくことになるでしょう(3%か?)。このデジタル通貨は、銀行が貸し付けに回すこともできます。
【歴史】
明治15年(1882年)の日銀の設立前の、明治維新のとき、江戸幕府のあとの維新の税制が整っていなかった政府は、戊辰戦争と西南戦争の戦費として、国債ではない政府紙幣を4800万両(1両が約30万円なので、14.4兆円)発行しました。
この金額は、維新のGDPに対し3倍は過剰だったので、当時の主産物のコメと物価が3倍に上がるインフレを生んだのです。(注)実質所得の増加はなかったので、都市部の世帯(30%)はコメが1/3しか買えない貧困さでした。当時は70%が農家の経済でした。
このインフレは、政府が日銀を作り、「1両=金1グラム=1円=1ドル」とする金兌換(きんだかん)の円の発行で、10年がかりでおさめたのです。
これは、通貨発行を抑制する強烈な引き締め策であり、太政官札の過剰発行で3倍に上がっていたコメが、日銀設立のあとの10年で1/3に下がっていくデフレになったのです(松方デフレ:10年間)。(松方デフレ:田中安興氏)
file:///C:/Users/yoshi/Downloads/78-tamura%20(3).pdf
GDPも、10年後の明治25年になって、やっと明治15年(1882年)にもどりました。
・インフレの原因は、内戦だった戊辰戦争と西南戦争の、戦費支出でした。
・10年デフレの原因は、3倍のインフレをおさめるための、日銀による金兌換の円の発行を、太政官札の増加率より縮小したことでした。
以上は、現代にも通じる通貨発行の原理です。
■11.三菱UFJとみずほが共同でデジタル通貨を発行(2024年)
政府のデジタル通貨発行(想定は2025年)に先がけて、銀行通貨のデジタル化(ブロックチェーン方式)が、発表されています。
政府のデジタル通貨になると、基軸通貨のドルへの外為交換と、SWIFTでの海外送金を行っている国際銀行(メガバンク)の役割は小さくなります。
そこでメガバンクが、円のレートと連動するステーブル通貨を発行して、円をデジタル化するものです。(仮称をプログマ・キャッシュとします)
この変化は、1970年代の、銀行の「オンライン化」のとき、クレジットカードが増えて、現金決済が減っていったときと、外形ではおなじ変化です。
「オンライン化」で送金が即時化して、VISA、マスター、アメックスなどのクレジットカードの利用が増えたのです。米国では、95%の買い物がクレジットカードでしょう。車すら、クレジットカードで買います。ラスベガスでは住宅の購入も使用額が無制限のカードで、受け入れていました。
BRICS+産油国+グロバルサウス(41カ国の予定)の、貿易通貨の、「R5(アール・ファイブ)」によるデジタル化に、対抗する動きです。
新会社の「プログマ」には、三菱UF、みずほ信託、三井住友信託が出資しますから、銀行系の「円のデジタル化」では、たぶん50%以上のシェアを占めることになるでしょう。
利用者は「新しいデジタルクレジットカードの通貨」と考えていい。
現在、貿易では以下のように、ドル基軸が介在する仕組みで輸入原油の決済が行われています。原油以外のエネルギー、金属資源、穀物(コモディティ)、肉や魚の食品、ユニクロの衣料やニトリの家具など多様な商品の輸入決済もおなじです。
【現在の貿易決済】
「輸入商社の円預金→外為銀行でドルに交換→ドルで送金(SWIFT回線)→輸出会社の外銀の口座へドルが入金」。これがドル基軸での輸入決済です。
送金時間に約2日、通貨交換の手数料と送金量では約3%という高いコストがかかっています。28.1兆ドル(4000兆円:2021年)の、世界の貿易通貨の60%(2400兆円)にはドルが介在していて、これがドル基軸です。
1年に2400兆円のドル買い/ドル売りがあるということです(1週で45兆円)。ドルレートは、1週平均24兆円の、世界からのドル需要で支えられています。
【変化】
「プログマ・キャッシュ」を貿易通貨に使うことを、輸出会社と輸入会社で合意すれば、貿易決済は以下のように変化します。
◎「輸入会社プログマ・キャッシュの預金口座→ブロックチェーンで送金→輸出会社のプログマ・キャッシュの預金口座」。
送金は即時化し、手数料は1%付近という。輸出入の会社は、殺到していくでしょう。ドル基軸のSWIFTの、一般的な3%付近の手数料と、2日の送金時間は、時代遅れのものです。2%の差は大きい。1億ドルで300万ドル(4.2億円)です。
ドル基軸のSWIFTを使う必要がない。つまり「ドル基軸はなくなる」。(注)この変化を5年とすれば、5年後の米ドルは、現在の146円から、1ドル70円に下がっていくでしょう(推計)。
政府のCBDCとプログマ・キャッシュ(仮称)はおなじ価値をもつものです。
プログマ・キャッシュの口座を作るだけで、送金・受金に、個人であっても利用ができます。クレジットカード番号のような口座番号、パスワードをもらえばいいだけです。取り扱いは、仮想通貨のビットコインとおなじです。
政府は、プログマ・キャッシュの利用を禁止にすることはできません。世界の他の銀行グループも、陸続(りくぞく)と作るでしょう。JPモルガンも作っています。これは、通貨の「インターネット化」です。アマゾン、アリババ、楽天ができたような変化です。
ユーザーの使い方は、ソフトバンクの電子マネーのPAYPAとおなじです。商店の二次元コードをスマホで読み込めば、決済が完了します。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB086MI0Y3A900C2000000/
2024年から実用化される予定ですから、あと1年。
【後記】
たぶん2025年が予定されている政府のデジタル通貨(CBDC)の前に、このように、銀行系のブロックチェーン型デジタル通貨が、普及するでしょう。
CBDCは、一般会計と特別会計の政府の財政支出(総額250兆円)部分になっていくでしょうか。
個人は、現在のクレジットカードやポイントカードのように、財布に何枚かのデジタル通貨のカードをもつことになります。銀行は、現在の、仮想通貨の取引所になっていきます。
ブロックチェーンの通貨のホンモノ認証は、桁数の大きな素因数分解で行います。素因数分解では、計算速度が速いスーパーコンピュータの総当たりの計算で解くしか、方法がないからです(RSAの暗号)。通貨では、ホンモノ、ニセモノの認証が命です。
われわれは、紙幣を見て、1万円札の認証を無意識に行っています。紙幣に偉人の顔が使われるのは、人間は、人物の顔に、もっとも敏感だからです。
ごくわずかの微妙な目の動き、頬、唇の表情でも印象は変わります。お化粧が習慣の女性は、知っているでしょう中島誠之助のTVでの、知識による骨董の鑑定(=認証)も、これとおなじです。
79年、ドルの金兌換制(29年)、ペトロダラー制(50年)で続いたドル基軸は、たぶん5年で終わります。いや3年か?【ビジネス知識源プレミアム・アンケート:感想は自由な内容で。 以下は、項目の目処です。】
1.内容は、興味がもてますか?
2.理解は進みましたか?
3.疑問点はありますか?
4.その他、感想、希望テーマ等
5.差し支えない範囲であなたの横顔情報 があると、今後のテーマと記述の際、より的確に書くための参考になります。
コピーして、メールに貼りつけ記入の上、気軽に送信して下さい。
感想やご意見は、励みと参考になり、うれしく読んでいます。
時間の関係で、返事や回答ができないときも全部を読みます。
時には繰り返し読みます。【著者へのひとことメールおよび読者アンケートの送信先】
yoshida@cool-knowledge.com本ウェブマガジンに対するご意見、ご感想は、このメールアドレス宛てにお送りください。
配信記事は、マイページから閲覧、再送することができます。
マイページ:https://foomii.com/mypage/
【ディスクレーマー】
ウェブマガジンは法律上の著作物であり、著作権法によって保護されています。
本著作物を無断で使用すること(複写、複製、転載、再販売など)は法律上禁じられています。
■ サービスの利用方法や購読料の請求に関するお問い合わせはこちら
https://letter.foomii.com/forms/contact/
■ よくあるご質問(ヘルプ)
https://foomii.com/information/help
■ 配信停止はこちらから:https://foomii.com/mypage/