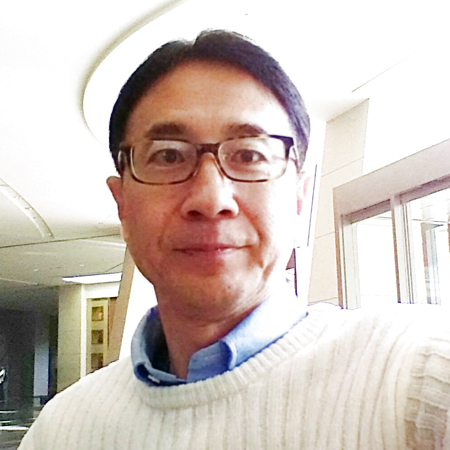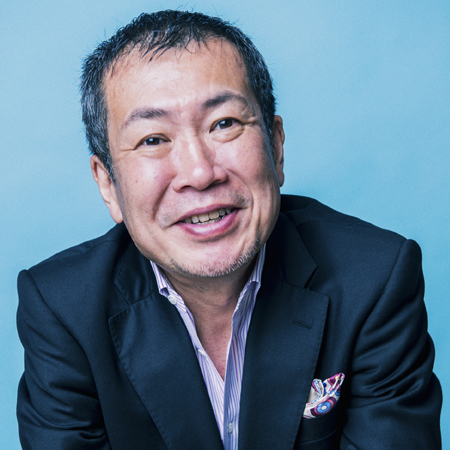■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
<1ヶ月にビジネス書5冊を超える知識価値をe-Mailで>
ビジネス知識源プレミアム(660円/月:税込)Vol.1369
<Vol.1369号:スタグフレーションに向かうG7と中国の不動産の危機(1)>
2023年9月24日:通貨の大転換に向かっている世界シリーズ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホームページと無料版申し込み http://www.cool-knowledge.com
有料版の申込み/購読管理 https://foomii.com/mypage/
著者へのメール yoshida@cool-knowledge.com
著者:Systems Research Ltd. Consultant吉田繁治
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
ウクライナ戦争は、事実上の終結に向かっています。
1)直接には、6月からの反転攻勢の成果がなかったこと、
2)間接には、米国でウクライナ支援反対がCNNの調査でも55%に増えたことです。
CNNには民主党政権への偏向があります。実態では65%以上の反対でしょう。米国のメディアは、政治的です。医療・軍事も政治的です。
学校(大学)も政治的です。米国民は納税者の政府への権利意識が日本より高い。政府を成立させている納税者の意識は、日本では、伝統的に低いように見えるのです。
理由は、「民主制の政府は自分たちが作っているという認識がない」からでしょう。政府は国民の納税があって成立している機関です。国民が納税を放棄すれば、株価がゼロになった企業のように消えます。
自分の所得から納税するのは、なぜでしょうか。考えたことがありますか。
税と社会保障の負担率が、所得の53%を超えています。われわれの所得の過半を使っている国家の根底を、考えるべき時期でしょう。
憲法には、国民は勤労と納税の義務があると書かれています。しかし学校教育は、納税の義務の意味を教えていません。
「義務」は、本質的には、1)愛(事例:子供への愛から養育義務が生じる)、2)または何らかの報酬(事例:会社から賃金をもらうから働く義務が生じる)によって、生じるものです。では、政府が国民にもたらす報酬とは何か?
なお人間の精神で崇高なものである愛は、自己犠牲でしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<Vol.1369号:スタグフレーションに向かうG7と中国の不動産の危機(1)>
2023年9月24日:有料版・無料版共通
【目次】
■1.政府の税収は最高になったが、国民の実質所得は3%減
■2.米国両院での法案、予算案の成立プロセスは複雑
■3.国民の支持よって成立するのは独裁国も同じ
■4.古ぼけた用語ですが、公僕の精神
■5.2000年代から家産官僚制の問題が大きくなってきた
■6.家産官僚制を続ける日本には、とくに国民投票制が必要
■7.未来が閉塞状況の現代日本
■8.国民負担率(=官の経済)が50%以上になった
■9.大きな政府の原点、ケインズのマクロ経済学理論の誤り
■10.国民負担率が高くなると経済は成長しなくなる
【後記】
<Vol.1370号:スタグフレーションに向かうG7と中国の不動産の危機(2)>
2023年9月27日:有料版のみ
【目次予定】
■11.中国には不動産統計のいい加減さがある
■12.銀行の不動産向け融資
■13.中国の不動産危機は、どうなっていくか
■14.日本の資産バブル崩壊の規模とプロセス
■15.中国の不動産バブル崩壊と、その後の経済予想
■16.中国の、不動産価格下落からの不良債権は989兆円
■17.中国の株価のPERは日本の半分
【後記:本稿の方法】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1.政府の税収は最高になったが、国民の実質所得は3%減
日本では、消費税が10%(23.9兆円)上がりましたが3年から5年後には防衛費の2倍(5.5兆円→11兆円)と医療費の急増から13%か15%に上がるでしょう。納税者の政府への権利意識は、米国以上に高まっていい。
2022年度の総税収は71兆円あって、史上最高額です。
政府予算の114兆円も最高額、財政の赤字は43兆円であり、国債の増加発行になります。つまり官の経済は、民の経済を圧迫して増え続けます。
◎とくに1000万人の団塊の世代が、自然の推移で後期高齢者(75歳以上)になると、医療費と年金支給額が増えるので、2023年以降2040年までは、官の経済は大きく増えていきます。75歳以上の一人あたり医療費は92万2000円です。
45歳から64歳までの平均医療費は28.2万円ですから3.3倍です(厚労省)。経済の成長率は低いので、税金と社会保障保険の増額でまかなうしかない。厚労省は、国民に「年はとるな、病院にかかることも抑制しろ」とは言えません。
https://www.mhlw.go.jp/content/nenrei_r01.pdf
【国民の実質所得は3%低下した】
物価上昇率を引いた国民の実質所得が減る(-3%)なかで、税と社会保障費が増える。この傾向を作っている基礎は、人口減と、高齢者(65歳以上)増加、生産年齢人口の減少ですから、自然の動きです。
働くの中心である現役世代(15歳~64歳)は、20年で1287万人(-18%)減ります。約20%も働く人が減る社会は、どうなるか。
・2040年の、人口の年齢構成(構成比:増減)
〔2020年〕 〔2040年〕
65歳以上 3600万人(29%)→3928万人(35%:+9%)
15歳~64歳7500万人(59%)→6213万人(55%:-18%)
15歳未満 1260万人(12%)→1142万人(10%:-10%)
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001093650.pdf
物価が上がると、10%の消費税は、物価×1.1ですから、物価上昇×10%分が、自動的に増えていきます。名目所得が増えると、課税率が上がる累進課税とならび、消費税も巧妙なものです。
2022年から23年の、官の経済の税収は最高になった。しかし民の経済の、国民の実質所得は減った。今後、もっとひどくなっていく。フランスなら革命が起こるくらい「とんでもない経済に向かっている」のが現代日本です。政治家と国民が静かなのは、不思議です。
政府を相対的に見るフランス人なら暴動でしょう。フランス革命の伝統をもつ国です。日本人は政府を相対的なものと見ているのか。政府は自分たちが、納税によって作ったものだという意識はない。
選挙が命である政権は、米国では、国民の世論での反対がほぼ60%を超えるあたりから、政策の実行が難しくなります。日本では、反対が70%あたりでしょうか。
日本国民は、二大政党(50:50)の米国より、自民党一極です。
政権に不都合なことがあっても、結局、政府を支持する固定票(約35%か)の比重が大きくなります。
野党が支持率を増やさないのは、外交と内政に「国家のビジョン(こうあるべきだとする姿)」がないからです。政権のスキャンダルや不都合をあげつらうことに終始しています。
■2.米国両院での法案、予算案の成立プロセスは複雑
2022年の中間選挙から、米国下院では、反民主党の共和党が多数派です。ウクライナへの支援を含む、2023年度の政府予算案に否決の動きがあります。下院で予算案が否決されれば、修正予算が再上程されます。
その間、つなぎ予算が成立しないと、政策の実行ができず、政府機関の一時閉鎖(公務員のレイオフ)になります。日本では公務員のレイオフの事例はない。日本政府の国債発行には、米国のような法的な上限がないからです。政府負債の、法的な限界は議会で作れますが、自民党は行いません。
政策とは、軍人+公務員の俸給+政策費、つまり政府予算を使うことです。とくに問題になっているのは、ウクライナへの軍事支援予算です。下院で否決されると、成立は困難になります。
共和党は、財政赤字の緊縮を求めています。2023年度の財政赤字はGDP比で5.8%と大きい(1.4兆ドル:200兆円:国債残は32兆ドル:4480兆円)。緊縮を求める共和党がない日本は、GDP比7.5%の赤字です(41兆円:財政への国債残は1068兆円:地方を含む政府債務は1452兆円)。
(わが国の財政事情:財務省主計局:2023年度予算案)
https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2023/seifuan2023/04.pdf
(政府の総債務は資金循環表の1ページ)
https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjexp.pdf
米国には、日本にはない「議会(=国民の代表)が政府に課す債務上限」があるため、財政赤字(1.4兆ドル)と累積赤字(32兆ドル)の増加は、政治的に深刻です。現在、日米両国が等しく財政危機の状況です。
米国共和党の保守派は、財政が赤字の米国がウクライナへ支援することに反対しています。議員は世論を睨みながら動きます。世界に共通です。
■3.国民の支持よって成立するのは独裁国も同じ
中国、北朝鮮、サウジ、UAE、クウェートのような、現代の王制の独裁国であっても、国民からの支持が40%はないと政権は倒れます。この点では、選挙民主制の民主国と変わらない。中国共産党(9800万人)では、いま、「閥の抗争」が起こっているようです。
天皇制や西欧の王制すら、国民からの過半数の支持で成立しています。
反対派が多ければ、議会の立法で一般会計の皇室予算をゼロにして、なくすことはできます。お金がなければ。皇室も維持ができない。どこかで働いてマネーを得る天皇になるからです。あるいは国有林のあがりか、伊勢神宮の賽銭か。
働くことは、商品を買うお客が評価してくれる仕事をすることです。
仕事は「事に仕えること」ですが、その「事(こと)」は顧客です。
公務員の仕事は、所得税と消費税を払う国民に、仕えるべきものです。
これが、王制ではない民主制の公僕である公務員がもつべき基本精神です。
(注)会社勤務は、上司と顧客に30:70で仕えることでしょう。組織という無形のものも、人格、人格の精神であるビジョン、経営では戦略起案力と実行力で考えると、具体的になります。
■4.古ぼけた用語ですが、公僕の精神
国民の健全と幸福以外の目的は、公務員にとって正当なものではない。
現在の公務員の、何%の公僕の意識があるでしょうか。ないとすれば、顧客のために働かない社員と同じです。顧客奉仕のビジョンをもつ会社なら、解雇に値します。
小さな事例ですが、他にも共通なことが多い、顧客への奉仕の精神が皆無のビッグモーターと、国民に損害を与える不正で癒着している損保ジャパンには、市場経済の本質を壊す堕落があります。
これは資本主義を奉じる国家への、反逆罪に相当する犯罪ですが、政府と損保に、その認識はあるでしょうか。たぶんない。資本主義の精神を壊す犯罪という認識がないからです。企業の品質偽装も同じように重罪でしょう。
【米国では公務員にレイオフがある】
報酬と予算をゼロにすれば、行政の活動はできない。これが米国の州と都市には多い予算不足のための公務員のレイオフです。
この面では、米国の民主主義は機能しています。
政府(=国家)は、税収+国債発行の政府収入と、獲得した政府収入の配分で予算が成立します。政府もお金で成立している機関ですら、日本ではこの30年、収入を増やす増税に傾斜するのです。
企業が赤字ならどうしますか。経費を効率化し、もっと売れる商品を作ります(顧客の評価が高い商品)。ところが政府は、国民への懲罰である増税です。いい加減なものだと思いませんか?
人気があったTVドラマのビバン(Vivan)のテントによる、孤児を集めて養育するマネーは、税金ではなく、テントの違法事業から得られものでした。こうした政府の成立の形態も、ありますが。ところが世界の政府は、公共の福祉という美名の影で、営利事業を行わないようになってしまった(これは偽装です)。
日本では、350万人の公務員が、市場で競争する営利事業を行ってもいいと考えます。なぜ実行しないのか?
なお国防、警察、司法は営利事業ではないので、予算案を国民投票にかければいい。裁判では、訴訟費用を有罪の被告人に罰金に加えて負担させればいい。
犯罪の罰金を、資産を売って一生かけても払えないくらい大きくすれば、犯罪は減っていくでしょう。払えないときは、身柄拘束で、国民のための強制労働で払うことになります。分野はいいくらであります。
公共設備作り、インフラ作り、補修、防衛です。
国の敗戦のときは、国を罰するものとして、要求される賠償金を払います。これと同じです。
実は、大きな罰金が効果的な犯罪防止になります。犯罪のほとんどは、金銭か、性的なものへの不当な欲望から、起こっています。
犯罪の利益が「割に合わなくなる」ようにすればいい。これも刑法の改正で可能です。刑法学者の固まった頭を変えればいい。
更生を目的にする懲役や禁固ではなく、いまの50倍、100倍の懲罰にすればいい。これも国民投票で決めることができます。
準公務員が行う営利事業のイメージは、医療です。医療の診療費は、国民医療保険(=医療費の前払い)から70%が支払われています。医師、看護士、薬剤師は、患者の生命と健康のための医療をして、働いています。
国民の承認を得られる政策の実行を、点数化すればいいだけです。厚労省は、複雑な医療・診療を点数化しています。不可能ではない。部長が点数をつけ、政策実行の、仕事の配分をするのは課長にすればいい。
これが、税を専有せず、国民を支配しない準公務員の仕事のイメージです。政治・官僚組織による国民支配は、政府の収入が、強制して徴収する税収であることから来ています。
■5.2000年代から家産官僚制の問題が大きくなってきた
税と社会j保障保険は、国民がおさめたもので、国民に所有権があるものですが、日本の「家産官僚」は、税を専有しています。
おさめた税(公金という)は、原理的には納税者が所有権をもつものですが、官僚織機が分配と差配権を専有しています。これが、王家が淵源の、家産官僚です(マックス・ヴェーバーの定義)。
封建時代には、税は王家の所有であり、官僚は、王家の家産官僚でした。民主主義では、官僚は、王(=封建領主)ではなく国民に仕える公僕にするべきなのです。
専有は、難しい民法の用語です。専有は、所有ではなく事実上の支配権です。株式会社は、株主の所有物ですが、株主から支配権を委任されたエージェントとしての経営者(CEO)が、経営権を専有しています。これが所有(株主)と専有(経営者)の違いです。
専有は、事実上の支配権です。
株主(=国民)と、国家の経営実行者(=官僚)の関係です。
わが国の家産官僚制に対しては、株式会社のように、チェック機関として株主総会での採決が必要でしょう。
この株主総会が「政府の法と予算の可否への、ブロックチェーン投票」です。現代の官僚制への国民投票には原理的な根拠があります。
民主主義の代議制は、国民投票の実行がムリだったから作られた制度です。
インターネットのブロックチェーン投票(スマホ)なら、法案と予算案の全部を国民投票にかけることできますから、古代ギリシアの直接民主制のインフラになるのです。世論調査などという、「胡乱(うろん)なもの、あやしいもの」は要らない。
■6.家産官僚制を続ける日本には、とくに国民投票制が必要
政府部門(税収+赤字国債発行=財政支出)が、GDPの50%以上占めている日本や欧州にとっては、家産官僚制をチェックする国民投票がないと、民間の所得は、税と社会保障費の国民負担に過半をとられて、官僚の経済になって成長しなくなります。
これが、社会民主制の西欧・北欧であり、日本です。
【企業には、資本の所有者の株主総会がある】
株主総会がある国家に変えれば、350万人の政府(中央政府+自治体)の公務員が、医師が行っているように、国民の役に立つことを行って、医師のように収入を得る方向に変わらざるを得ない。
医療は公的な性格ももちますが、民間医療にしたのです。
民間の所得が増えているスイスのような直接民主制は、主要な政策と法に国民投票があって、国民投票制に近い。スイスのEUやユーロへの加盟は国民がノーとしたので、独立を守っています。
【ブロックチェーン投票ができる】
インターネット時代の国民投票は、手間とコストはかからない。偽造ができないブロックチェーンで、携帯電話やコンピュータからの投票にすれば、1日に数回であっても、企業の売上のように瞬間に自動集計できますから、実行できます。
安定した政府にならない? 民の所得が安定すれば、政府が安定する必要が、どこにありますか?
国民投票制になれば、国民が評価する法案・予算案を作らないと、政策は実行できない。企業と同じです。顧客が評価する商品を作らないと、企業は消えます。
【ポピュリズム批判への反論】
ポピュリズムでは、短期的な利益を求める予算と法になる?
ポピュリズムの否定は、知的なエリート(学校成績の上位者)が、庶民より国民のためにいい政策や法を、つまり「倫理的な善」を作ることができるという観点からのものです。では、尋ねます。
企業の商品はエリート階級ではない大衆である庶民の、購買という投票数での評価です。企業が売上のポピュリズムから、変な商品を作るようになってきたでしょうか。事実は逆です。
どこかは言いませんが、エリート意識が高い企業(政商と武家の商法)こそが、ポピュリズムの評価が低い商品を、作って潰れてきたのです。例えば、代表的な準公務員である金融は、武家の商法です。NNT、NHK、過去の国鉄も同じです。
(注)銀行マンを準公務員と言うのは、金利は事実上、政府が決め、不良債券からの危機のときは、政府・日銀から救済されてきたからです。ダイエーも、経産省から救済されました。予算の決定権が議会にあるMHKも準公務員の組織です。このためNHKの報道は、国民から視聴料をとっていながらも、政府政策寄りです。
ユニークなマイナンバーで紐付けすれば、国民投票は技術的に可能になりました。政策の全部、法案の全部を、国民投票にかけ、ブロックチェーン投票数で、過半数の賛成が得られたものを実行可とする。
【政治家と議会は不要】
国民投票制にすれば、代議(=国民エージェント)の政治家と議会は必要がなくなっていきます。法、予算案を作り、執行を管理する公務員の組織があればいい。憲法を改正すればこれが行えます。政治はその程度であっていいの。以上が政治の、根底からのイノベーションです。
21世紀は、インターネットと投票偽造ができないブロックチェーンによって、これを唱える政党が出ても実現できる時代になっています。
政党も、個人献金を報酬とする公務員上級職(法案作成の決定権をもつ)にすればいい。決定権は、法案を作るところまでとする。
法案が実行されるかどうかは、国民投票で決める。支持の低い政党には個人献金が集まらない。個人献金の少ない政党は潰れていく。政党は、法案という商品を作って、国民に売る。ここも、民間企業と同じ売上のポピュリズムにする。
■7.未来が閉塞状況の現代日本
◎人体の血管のように、縦横に張りぐめらされた既得権益が阻害してきた、「現代社会の閉塞を打破する唯一の方策」が、ブロックチェーンによる全部国民投票制の、完全民主主義でしょう。5公5民の国家は、民間経済は50%でしかなく、成長しません。
閉塞とは、現在の経済が悪いということでない。人間は、未来を想定して現在を評価します。日本に未来の輝かしい経済があるでしょうか? 現在より、よくない未来が想定されるとき、閉塞という。
高齢化と少子化で、世界の先頭を走り「大きな政府になった日本」には、とりわけ2020年代の構造転換が必要です。構造転化がないかぎり未来は暗い。
暗くてもいいのなら、それでいい。しかしやはり「トンネルを抜けると雪国の朝だった」という展開が欲しい。
■8.国民負担率(=官の経済)が50%以上になった
19世紀の近代社会が、20世紀の、官の利権が介在した社会福祉を柱にした現代社会になる過程で、政府の予算(財政)の割合がGDPの50%を超えるように拡大し、先が見えなくなっているのが現在でしょう。
官の経済が50%以上を占めると、民間の所得(=民間のGDP)は最大でも2%/年しか伸びなくなります。平均では1%台または0%台の成長がせいぜいになる。
日本の、潜在国民負担率は、財政赤字を含むと、53.9%です。
(国民負担率の国際比較)
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/futanritsu/sy202302b.pdf
国民の手取り所得である可処分所得〔=所得-(税+社会保障費)〕の53.9%が、税と社会保障費の負担です。給与明細を見れば個人負担分が出ています。これと別に企業も個人負担分と同じ社会保障費を払い、所得税を払っています。加えて、物価に含まれる消費税が10%です。消費税は23兆円に増え、かつては一番大きかった所得税(21兆円)を超えています(2023年度:財務省)。
こうした国に、将来があるでしょうか。現在の日本は、所得では江戸時代の5公5民に回帰しまし、防衛費が2倍になるのでしばらくすれば6公4民になります。
53年前、1970年の国民負担率は、いまの半分以下の、24.9%でした(3公7民)。当時は、財政は赤字ではなかったので、国債もなかった。国民の負担は、現在の約半分だったのです。
その後、毎年1.6%増えてきました。
福祉国家を言う政府予算の拡大が、ツタのように、官僚権益と、政府予算を受注する政商の権益をはびこらせてきたのです。これは、先進国の世界に共通です。
行政官僚が権益をもつことなっていく福祉国家を掲げた、第1次石油危機の1970年代から、先進国共通に、国民負担率が上がる一方になったのです。
■9.大きな政府の原点、ケインズのマクロ経済学理論の誤り
ケインズが発見したマクロ経済(『一般理論』)は、個人と企業のミクロ経済の国民経済では解決ができないとしたことも、国債を発行する政府予算を拡大させきました。
所得が増えた世帯が、消費増加分より貯蓄を増やしていくと、経済の全体(マクロ経済)では「供給>需要」になって、経済は不況化し(企業の売上は減って)、失業が増える。
設備投資サイクルなどの、景気循環からの不況のときは、政府が、増えた貯蓄を国債で吸収し、公共事業を行って有効需要を作ればいいとしたのです。需要不足(供給>需要)への、短期の不況対策では正解です。しかし、長期では正解ではない。
理由は、民間企業の商品供給力は、政府の国債発行と公共事業の増加では、増えないからです。
所得=商品消費+貯蓄です。貯蓄率が高まると、所得のなかの商品の消費割合は減っていく。企業の商品供給力に、余りなかます。
↓
企業が作った商品が売れ残るので、雇用をカットし、商品生産を需要に合うまで減らす。これが、不況です。
↓
ケインズは、不況のときは、政府が国債を発行し、需要を増やせば、供給力に見合う需要に回復し、経済は正常化するという提案をしたのです(『一般理論』)。これは、政府のマクロ経済のない古典派経済に依拠していたマルクスの資本論への反撃でもありました。
↓
ところが・・・政府の公共事業は、企業の設備投資ではないので、商品供給力は増やさない。国債の発行と財政の拡大(財政は政府需要)が長期に続くと、需要が供給力を上回って、インフレになっていく
↓
一時的には増えた公共事業から需要が増えても、国債では企業の供給力は増えない。その後は、物価上昇>賃金上昇の結果になってく結果を生んだのです。物価が6%から8%上がり、賃金は3%から4%しか上がらない経済です。個人の生活は苦しくなっていく。
これが70年代、80年代の米欧のスタグフレーションでした。もっともヒドかった国は、民間の生産力が弱いケインズの英国でした。
日本では1989年までは、所得の増加率が世界1大きく、民間設備投資も世界1大きかったので。スタグフレーションにはならず、資産バブルになったのです(1985-1989)。
現在の、ひとつの例を挙げれば、経済のコストである物流費の高騰です。コンテナ輸送費は、数倍にあがっています。輸送費は、最終物価の5%部分です(GDPの5%)。2倍に上がると、10%になります。タクシーも目に見えて減っています。
米国では、物流費の約50%を占めるドライバーの賃金が15万ドル(2100万円)に上がって、店舗の物価上昇の原因になっています。
政府が予算を拡大した石油危機のあとの、スタグフレーション(所得の増加率<物価上昇率)もこれでした。
◎現在、つまりコロナのあとの政府予算の拡大(日米欧が共通にGDPの約20%)のあと、エネルギー・資源の輸入消費をするG7(先進国)はスタグフレーションに向かっています。
2023年の、日本の実質所得は、平均でマイナス3%です。欧州は日本とほぼ同じです。株価上昇と金融経済が大きな米国では、時価総額が6000兆円(日本の7.5倍)の株価が、20%から30%下がると、欧州と同じスタグフレーションになります。
(2023年末あるいは2024年3月からと予想)。
■10.国民負担率が高くなると経済は成長しなくなる
国民負担率が高い国では、
・官のエリートが決める行政予算が増えていくので、
・民間の、ポピュリズムの市場経済を、圧迫して成長しない。
(国民負担率 1970-2023)
政府予算である医療費(40.8兆円)、年金(58.9兆円)、介護費その他の増加(31.5兆円)、合計で131兆円に増加(GDPの24%)では、経済は成長しません。
(国民負担率の推移1970-2023)
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/futanritsu/sy202302a.pdf
(日本の財政)
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12654173/www.mof.go.jp/policy/budget/fiscal_condition/related_data/202210_01.pdf
「国民投票法」を作れば、行政の制度と法案の国民投票制を実行できます。「れいわ」の山本太郎さん、この法案の原案を作ってみませんか? 山本太郎氏の政治信条に合うでしょう。いま、日本は、根底からの改革が必要です。消費税廃止の政策では、寒いだけです。
公約にして、多数の候補を立てて次の衆議院選挙を戦えば、議会での政権選択のキャステング・ボートの議席を取れるかもしれません。
いまこそ、既存の政治と行政の体制を転覆する発想を、もたねばならない。インターネットとブロックチェーンがある現代は、全部国民投票制は、幻想的な制度ではない。20年後の未来のための、日本の根底からの改革です。
代議制の民主主義革命が、国民負担の増加で行き来詰まったあとの、全部国民投票制(直接民主制)への改革です。現代の代議制は、国民の全員が政治に参加できないため、国民の代理(代議士=議員)を作って議会を構成させたものです。古代ギリシアのような、全部国民投票制(直接民主制)は、インターネットのブロックチェーンで実現します。
国民負担率が、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%・・・・と高まっていく日本を、希望しますか? 所得が2%増えて、物価が2%上がり、国民負担率が1ポイント/年で増えれば、毎年1%ずつ貧困になっていくのです。
先に待つのは国民皆貧困です。高所得者は、海外に脱出でいくでしょう。海外からインターネットでリモートワークができるからです。医療すら、遠隔が可能になっていきます。IT開発では、会社に行く必要はない。事務も同じです。コンピュータ化は、リモートワークということです。
【後記】
Vol.1369号:スタグフレーションに向かうG7と、中国の不動産の危機(1)は、ここまでとします。この続きは、有料版正刊として、木曜日に送ります。
「全部 国民投票制」いかがですか。政府はマイナバーを作ろうとしていますが、インターネットのブロックチェーンによる国民投票制とセットにできます。有権者確認、不正投票の管理は自動化するからです。【ビジネス知識源プレミアム・アンケート:感想は自由な内容で。 以下は、項目の目処です。】
1.内容は、興味がもてますか?
2.理解は進みましたか?
3.疑問点はありますか?
4.その他、感想、希望テーマ等
5.差し支えない範囲であなたの横顔情報 があると、今後のテーマと記述の際、より的確に書くための参考になります。
コピーして、メールに貼りつけ記入の上、気軽に送信して下さい。
感想やご意見は、励みと参考になり、うれしく読んでいます。
時間の関係で、返事や回答ができないときも全部を読みます。
時には繰り返し読みます。【著者へのひとことメールおよび読者アンケートの送信先】
yoshida@cool-knowledge.com本ウェブマガジンに対するご意見、ご感想は、このメールアドレス宛てにお送りください。
配信記事は、マイページから閲覧、再送することができます。
マイページ:https://foomii.com/mypage/
【ディスクレーマー】
ウェブマガジンは法律上の著作物であり、著作権法によって保護されています。
本著作物を無断で使用すること(複写、複製、転載、再販売など)は法律上禁じられています。
■ サービスの利用方法や購読料の請求に関するお問い合わせはこちら
https://letter.foomii.com/forms/contact/
■ よくあるご質問(ヘルプ)
https://foomii.com/information/help
■ 配信停止はこちらから:https://foomii.com/mypage/