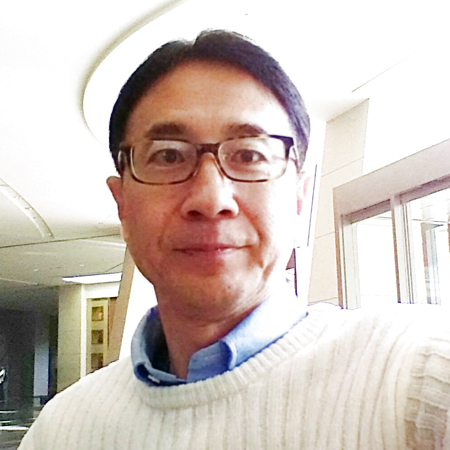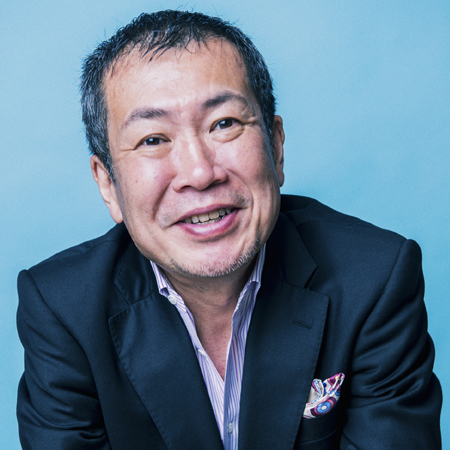<1ヶ月にビジネス書5冊を超える知識価値をe-Mailで>
ビジネス知識源プレミアム(660円/月:税込)Vol.1372
<Vol.1372号:増刊:インフレと金利と、世界の金融危機(1)前編>
2023年9月8日:通貨の大転換に向かっている世界シリーズホームページと無料版申し込み http://www.cool-knowledge.com
有料版の申込み/購読管理 https://foomii.com/mypage/
著者へのメール yoshida@cool-knowledge.com
著者:Systems Research Ltd. Consultant吉田繁治
世界の金融市場を見ると、
◎日経平均、米国ダウ、欧州株(ストック600)は、9月から10月初めは、明確に下落しています。
投資家の不安心理を示すVIX(期待年間変動幅)も、18.5%に上がっています(23年9月は14%付近でした)。
【1995年以降の金利ついての、基礎の知識】
9月から10月の株価下落の原因は、金利の上昇です。金利については、中央銀行が決めていると考えているひとが、圧倒的に多いでしょう。
実は、中央銀行(日銀や米国FRB)は、金利の誘導目標を示すだけです。実際の金利は、債券市場での国債の売買によって、株価のように日々変動しています。金利は一定ではないのです。
ところが債券市場では、個人の参加ほぼゼロであり、金融機関が売買しています。このため知られていないのでしょう。株の売買が価格を決める株式市場は、個人も参加しています。株価の基礎である金利を決める債券市場は、ほぼ金融機関だけの売買市場です。
中央銀行は、金融機関に短期融資するときの「公定歩合の金利(日銀0.1%、米国5.25%~5.50%、ユーロ4.25%)」は決めています。
しかし金融政策が、中央銀行による国債の売買市場への介入になった1995年以降は、公定歩合の比重は下がったのです。
◎1995以降、政府の負債証券である国債は、定期預金に銀行の金利がつく現金に準じる証券になっています。変動している国債の金利は、定期預金の金利に相当します。しかも円やドル国債は、通貨に近い、利付債券と見なされ世界200カ国の銀行の店頭で売買されいるのです。
以上は、1995年の金融ビッグバン(通貨の外為取引と金利の自由化)以降の変化です。日銀やメディアからの説明は、ビッグバンというだけで、金融の自由化の説明はなかった。ビッグバン以降はそれまで同じだった銀行預金の金利も、微妙ではあっても違います。
ビッグバン以降の、世界金融を決めている金利について説明ができる人は、少ないように思っています。ビッグバン以降は、外貨と海外の国債は、制限なく買えます。外銀へのドルの定期預金と米国債を買うことは同じ行為です。国内の銀行でも買うことができます。
(注)初めて米国に行ったとき、まだ資本の規制があって、旅行者はドルに確か5万円くらいしか交換できなかった。コーヒーが1ドル(280円くらい:日本では80円くらい)であり、ファミレスでコーヒーを頼むことも考えていました。本で読んだのですが池田首相と秘書官の宮沢喜一が外交で米国行ったときは、安いドライブインに泊まっていたという(1960年代;1ドル360円)。
◎1995年以降の金融政策は、国債の売買市場に中央銀行が介入して行う、「金利とマネー量の調節」です。
1)金利の上昇は、「国債の売り>国債の買い」です。買いが少ない国債の価格は下がる。既発国債の価格が下がることは金利の上昇であり、インフレや景気を抑制する金融の引き締めになります(現在の米国)。
2)逆に、「国債の売り<国債の買い」になると、売られる国債価格は上がって、金利は下がります。世界の債券市場の全体で、円国債の買いが増えることが、日本の金融緩和であり、景気の刺激策にないります。
日銀が、金融の引き締めと利上げ、または、緩和と利下げをしているように考えられているのは、日銀の、債券市場への売買の介入額が大きいからです。
【株価、証券価格の動きの基底にあるのは、長期金利の上昇】
株価と証券の価格は、金融の引き締めと長期金利の上昇によって、マイナスの影響を受けます。普通の時期なら、「インフレの発生→中央銀行による金融の引き締め→金利の上昇→債券と株価の下落」になるのです。
現在の米国とユーロがこれです。世界の主要国では日銀だけが引き締めをせず、長期金利は1%以下に抑えています。
9月の中央銀行金融政策とは無関係な、インフレ対応の市場の自律的な金利上昇の動きが、
・2024年の3月または6月からの、世界的な金融危機につながっていくか、
・あるいは短期的な波動か、本稿では、これを検討します。
*
1)国債の売買市場で決まる日本の長期金利は、日銀のYCCの長期金利の上限、1.0%に近い0.8%に上がり、
2)米国の長期金利も、4.7%に上がっています(9月以降、0.5ポイント上昇しました:これは、異常さのある上昇です)。
日米の金利差から、ゼロ金利の円を売って、4.7%の金利のドルを買う動きが大きくなって、1ドルが150円付近の、超円安になったのです(23年10月初旬)。
【売られている日米の国債】
金融市場では、残高1200兆円の円国債と、残高32兆ドル(4800兆円)のドル国債が、ともに、売り超になっています。
円国債の海外所有は、約10%の120兆円です。
ドル国債の海外所有は、約30%の1440兆円です。
【原因】
日・米の金利上昇は、
・両国の既発国債が売りのオファーの超過になり、
・売買の平均価格が下がったことを示しています。
国債の価格下落の結果が、金利の上昇となって示されるのです。
日本の金利は、コロナパンデミックが始まった2019年末にはマイナス0.2%でした。日銀が金融緩和(国債の買い増し)を続けいているなかで、市場の10年債の売買で決まる長期金利は1ポイントも上がったのです。
【日本の長期金利1ポイント上昇の意味】
2013年からの、日銀が、大量の国債(60兆円~80兆円/年)を買って行っていた「世界最初の異次元緩和」の末期の、2019年12月の日銀の国債保有は、484兆円でした。
異次元緩和が宣言なく終わっていた2023年10月は、586兆円へと、102兆円も増えています。
この増加は、コロナパンデミック対策として政府がGDPの約20%(110兆円)、赤字財政を拡大し、増加発行された国債を、金融市場ではなく、日銀が介入して買い受けたからです。
国債を、日銀が102兆円も買い増すことは、マネーの発行量を増やす金融の緩和です。
◎日銀による102兆円の国債の買い増し=金融緩和、つまり金利が0%の預金量の増加があって、普通は金利が下がるなかで、国債市場の長期金利がマイナス0.2%から0.8%へと1ポイント上がったことは、注目しておくべきです。原因は、円国債の世界での買いが減ったことです。
(円の長期金利の推移:SBI証券:金利が下がるときは円国債の買いが増え、金利が上がるときは円国債の買いが減っています)
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_PageID=WPLETmgR001Mdtl20&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&_ActionID=DefaultAID&burl=iris_indexDetail&cat1=market&cat2=index&dir=tl1-idxdtl%7Ctl2-JP10YT%3DXX%7Ctl5-jpn&file=index.html&getFlg=on
中央銀行が国債を買い増すときは、金融市場のマネー量(現金の量)が増えますから、普通、金利は上がらない。現在、普通ではないことが、債券の売買市場で起こって起こっています。
【金利上昇と、国債の価格】
市場の長期金利を決める10年債の平均残存期間は、約8年です。
↓
1ポイント金利が上がることは、市場の既発国債の価格が、1÷(1.01の8乗)=1÷1.083=0.923・・・7.7%も、時価が下がっていることを意味します。
【金融機関の国債の含み損は92兆円】
日銀と銀行・生損保がもつ国債の時価が、7.7%下がって、総額では、1200兆円×7.7%=92兆円の、評価額の損が発生しているのです。
この92兆円は、国債をもつ日銀+銀行+生損保の含み損になっていて、時価の自己資本を減らしています。
586兆円(国債発行残の49%)を持つ日銀は、7.7%時価が下がると、「国債保有額586兆円×7.7%=45兆円の含み損」を抱えています。日銀が、政府からの返済の満期前に国債を売れば、45兆円の損失が生じるという意味です。
【自己資本をなくして、債務超過になった日銀】
日銀の自己資本は、「引当金8.5兆円+準備金3.5兆円=12兆円」です。時価では、完全に債務超過(自己資本はマイナス33兆円)になっています。(注)この報道は、皆無です。
【1ドル150円の円安の、基底での理由】
日銀の債務超過は、円が価値と保っている国内ではなく、海外の銀行からは、「円の価値信用の低下」と見なされます。
国内では、円への、国民からの信用には大きな変化は見られない。しかし、海外金融機関は、「債務超過の日銀が発行した円の信用低下」を認識して、通貨の円と円国債を売ります。
↓
このため、日米の金利差(米国4.7%-日本0.8%=3.9%)と連動して、「1ドル≒150円付近」の円安と、日銀の金融緩和のなかでの長期金利の0.8%への上昇になっているのです。
以上は、国債価格、金利、通貨の原理的な関係です。以降は、具体論です。
<Vol.1372号:増刊:インフレと金利と、世界の金融危機(1)前編>
2023年10月8日:有料版・無料板共通
【増刊の目次】
■1.日本の常識は、世界の非常識
■2.約30年、円安イデオロギーが支配している
■3.GDP比の金融緩和がもっとも大きかった円の、独歩安
■4.円高が必要になった日本経済
■5.国益のために政府と銀行の、ドル売りへの転換が必要
【後記】
<Vol.1373号:正刊:インフレと金利と、世界の金融危機(中編、後編)>
2023年10月11日:有料版のみ
【目次と項目の予定】
■6.期待インフレ率と通貨の金利の、原理での関係
■7.米国の実質金利は高く、金融引き締めになっている
■9.実質金利のマイナスが引き起こした米国株価のバブル
■10.ロシア株のPERは、1.8倍
■11.米国と日本の長期金利の上昇
■12.中央銀行と銀行の同時債務超過は、「誰も言わない」
■13.FRBと米政府は、結局、どうするつもりか?
■1.日本の常識は、世界の非常識
◎「円が2021年までのように安全通貨」と見なされなくなった理由は、日銀の債務超過です。クレディスイスの破産があったスイスフランは、安全通貨のままですが、円は安全通貨から陥落しています。
(注)安全通貨とは、金利が低くても海外からの買いが多い通貨です。将来の通貨の価値信用が高い通貨です。円とスイスフランは世界から安全通貨と見なされていました。
【スイスフラン】
スイスフランは、マイナスやゼロ金利」のときも、海外の金融機関からは買われ金利が上がっても(スイス国債の価格が下がっても)買われてきました(買いの超過)。このため、スイスフランは長期金利4.72%のドルより上昇率が高い。
スイスの長期金利は0.95%と、ドルより3.77ポイントも低いにもかかわらず、いまも売りより買いが多い。これが、スイスフラン高の原因です(2021年の1フランは117円付→23年10月は164円=40%上昇:逆から言えば、円は40%低下)。
2年で40%は、金利換算では年利18%です。スイスフランに預金しておけば、円換算での預金が40%増えたということです。すごいものです。実は、スイスフランが強かったのではない。
◎インフレのなかで利上げができない円が弱かったのです。
【円と円国債】
ところが23年には海外の金融機関は、日本株と円国債は、金利が少しだけ上がるなかでは、売るように変わったのです(2023年から)。
◎計算すれば誰でもわかる、日銀の債務超過を知っている海外大手銀行から、外為市場では「円は安全通貨ではなくなった」と認識されはじめたことが原因だと判断しています。
2023円10月と、23年9月からの円安(1ドル≒150円付近)は、「円の価値低下の、世界的な認識による悪い円安」です。
■2.約30年、円安イデオロギーが支配している
「日本経済のためには円安がいい」という日本の常識は、世界の非常識です。
経常収支が赤字の米国と、経常収支がほぼ均衡しているユーロは、過去、一回でも「自国の通貨安がいい」とは言ったことがない。自国の通貨を下げる政策をとったこともない。通貨を上げる政策しかなかったのです。(注)経常収支=貿易収支+所得収支。米国は約50年、赤字を続けている。日本は2011年から貿易は赤字になった。しかし対外純資産418兆円からの、所得と配当が20兆円(5%)くらいあって、経常収支は黒字です。
(日本の対外資産と対外負債)
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/iip/data/2022_g.htm
日本にとっての円安は、世界の外為市場では、「円売り/ドル買いの超過」の結果を示すものです。
◎米国は、経常収支が構造的な赤字ですから(2023年は7287億ドル≒109兆円)、海外から、109兆円以上の「ドル買い」の超過、つまりドル高が必要な経済です。
このため日本には、ドル買いのために、「金融緩和、通貨増発による円安のイデオロギーを流した」と言えます(米国民主党派のクルーグマンが先頭です)
【円安でも、貿易は黒字にならなくなったのが2011年から】
◎2011年の3.11のフクシマ以降、貿易が赤字の構造になった日本にとっては、ドル建ての輸入物価が上がる円安は、国益を、ドル買いとして米国に売っていることになります。
もう12年も前から、日本は、構造的な輸出大国ではなくなっていたのです。(注)この分析も、なぜか皆無です。エコノミストは一体何をしているのか?
原因は、マクロのISバランスでの、貯蓄率の低下です。民間部門の貯蓄超過=政府の財政赤字+経常収支の黒字です。貯蓄の超過が減ると、政府の財政赤字は30兆円から40兆円はあるので、経常収支の黒字のなかの特に貿易黒字がなくなる経済構造になります。
貿易が黒字構造のときは、円に対しては、海外の物価を下げて輸入を増やす円安も必要でしょう。しかし貿易が赤字または均衡するときは、「円売り/ドル買い」としてジャパンマネーが、米国に行く円安は、国益の損になります。
↓
異次元緩和(=円の利下げ)の2013年から、日本の貿易は、赤字の基調です。
https://ecodb.net/country/JP/tt_mei.html
2013年-12兆円、14年-12兆円、15年-2兆円、16年+0.4兆円、17年+0.3兆円、18年-0.1兆円、19年-0.2兆円、20年+0.6兆円、21年-0.1兆円・・・9年の合計は、貿易赤字25.1兆円です。100円台にもどって、輸入額が減らないと貿易黒字基調にはならない。
この間、円とドルの実効レートは以下の、逆の動きでした。
・2011年100→2023年60:円の、世界の通貨に対する対外的な価値は、40%低下。
・一方で、日本が買ってきたドルは、実効レートが2011年100→2023年130へと30%上昇。
■3.GDP比の金融緩和がもっとも大きかった円の、独歩安
8年間の異次元緩和(=円の増刷500兆円)が始まった2012年からの、「奈落の底」にように見える円の、独歩安を見てください。ドル、ユーロ、人民元、スイスフランは上がっています。
https://honkawa2.sakura.ne.jp/5072.html
円だけが、ハイパーインフレのトルコリラや、アルゼンチンのペソのようにひどくはなくても、下がっていましす。
(円、ドル、ユーロ、人民元の実効レート)
以上の分析を政府・エコノミストはしてない。
日本の常識は、世界の非常識だからです。
円安が貿易黒字を増やすと思い込んでいるひとが、まだ多い。
(注)インフレを引いた実質所得が増えて、民間貯蓄超過が大きくならないと、どんなに円安になっても,日本の貿易黒字は増えません。預金を1年に60万円引き出す年金所得者が増えているので、日本の今後貯蓄率は上がりません。1990年代までにようには貿易は黒字にならない。
2012年には、1ドルは80円でした。ドル国債買いをして異次元緩和を開始したときから、120円台の円安になったのです。この円安で、2013年、14年、15年まで貿易赤字が逆に、増えました。
(注)海外生産と配当の所得である所得収支は、ドルで金額は同じでも、ドル高・円安で、円換算では増えたように見える為替差益の錯覚が生じます。
「錯覚(=幻覚)」という理由は、国内の円建て所得(みなさんの円の所得)はドル換算では、円安の分減るからです。
↓
日本の不動産、円預金、円の所得、円の商品価格、円建ての株価は、ドル高・円安では評価が下がります。1ドル100円から150円の円安の過程で、ドル換算では、33%も減ったのです。
日本の常識は、世界の非常識でしょう。
貿易が赤字の構造になると、円安は日本の資産と所得を下げて、物価を上げる「貧困政策」になります。これは経済学の常識でしょう。
2020年代には、韓国より所得が減ってしまい、米国の賃金と物価は日本の2倍になったのです。
■4.円高が必要になった日本経済
◎政府・日銀は、2023年から「円安イデオロギー」を捨てる必要があります。
為替介入(ドル売り/円買い)を、日銀と銀行によびかけて、100兆円行ってもいい。1ドル=100円にも戻って、物価、食品、電気・ガス・ガソリンも下がり国内経済は好況になります。
日本は、「ストック経済の国」になっています。
日本には、過去のドル買い(円安策)の結果である対外資産が、1338兆円、対外負債を引いた対外純資産が418兆円あります。
(財務省:対外資産、対外負債の、国のB/S)
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/iip/data/2022_g.htm
6か月で100兆円(1か月15~20兆円)なら、今日にでも国債・債券の売りのオファーを市場にす出せます。約1000兆円はあるドル建て債券の売りは、円買いになるので、円は上がり、ドルは下がります。
■5.国益のために政府と銀行の、ドル売りへの転換が必要
米国は、ドル高を国益としていますから、「おとなしかった日本の反抗だ」と驚愕し、緊急に特使を派遣して懇願外交をするでしょうが、対日戦争には決してならない。
米国への従属がとくに強い岸田さん、日本を貧困化させる、ドル買いの国策を、転換したらいかがでしょう。
◎サウジのサルマン皇太子が決めた「ペトロダラーからの離脱」も、米国への反抗です。貧国に向かっている日本が、いま、反抗すべき相手は米国です。
穴だらけのセキュリティでは守れない刺客が来ますか? 明治の西南戦争の西郷隆盛のように、反米の蛮勇をもつべきです(当時は反米ではなく反大久保利通)。対米従属の財務省は、岸田降ろしをしますが、それくらい何のこともない。
国民の税が所得である政治家は、国益のための覚悟が生命線です。世帯を富ませることが使命です。
岸田首相には、自己への誇りはないのか。近年の首相で、自尊の誇りが見える言動があったのは、第一次安安倍内閣のあとの福田康夫氏(2007-2008)でした。財務・金融担当相だった中川昭一のように、米国債の買いの要請を断ったのです。
【中川昭一という先例】
オバマ大統領のとき、米国が仕掛けた、ワインにハルシオン(強い睡眠薬)の朦朧会見から、非難を受けて辞任しました。民主党系が多いCIAは、こうしたことを裏で行う機関です。机には、銘柄を隠したシャンパーン見える瓶と、ワイングラスがあります。
ハルシオンは、夢遊病の状態を生みます。本人は、赤ワインをグラス一杯飲んだだけで、正常と思っているから会見に臨んだ。YOUTUBEの映像から見えるのは典型的なハルシオンの症状です。
泥酔しても飲酒では、こうした状態にならない。実は、中川昭一は、「日本は米国の、ATM(現金引き出し機)ではない」と米国の商務大臣に言っていました。後に支持団体から押されて政治家になった夫人は「自分は普通の会見をしたが・・・」と、あとで言っていたという。CIAの手口を知るために、記者の質問と中川氏の発言を聞いてみてください。
https://www.nicovideo.jp/watch/sm6177448
米国債を売ると言えば、「何かの方法での刺客が想定できますから、事前に準備をしておけばいい」。日本や中国の米国債をカストディ勘定で保護預かりしているFRBは察知しますが、構わない。中国やサウジは、米国債を売っています。
(中国の米国債・ドル債券の売り)
https://jp.reuters.com/article/usa-treasury-securities-idJPKBN2YY1V5
(サウジの米国債・ドル債券の売り)
https://www.moomoo.com/ja/news/post/26290461?level=1&data_ticket=1694268494407269
【ひとり、ドル買いを続ける日本】
2021年からの、世界インフレの中で、低金利の日本だけが、「円売り/ドル買い」をして、米国を支えています。このため、1ドルが150円付近の異常な円安になっています。(注)今日は149.22円。
日本経済、インフレ、世帯所得にとって良くない円安です。
長期的(2025年)には、1ドル=70円が、経済の均衡ラインでしょう。
◎物価の購買力平価でのドルは、所得、商品価格、不動産が2倍、過大評価されています。ドルの過大評価、円の過小評価の原因は、日米の約4%の金利差が促す、「円売り/ドル買い」です。
銀行と個人から、預金の金利がゼロの円を売って、MMFの預金金利では5%、国債なら4.7%金利がつくドルが買われているからです。
日曜増刊は、ここまでとします。
中編と後編は、水曜の正刊で送ります。
【後記】
1995年からの金融ビッグバンで、海外通貨の売買と、金利が自由化されたあとの金利については原理的なところが難しいので、本稿で具体的に示しました。
原理的な知識の提供はビジネス知識源の役割と考えているからです。ご理解されたでしょうか。いまでも日銀やFRBが決めている公定歩合を金利と考えている人が、98%でしょうか。
国債価格の変化によって金利が上下する原理を理解していないと、金利で動く金融の全体も分からない。
血圧(金利に該当)を理解しないで、血液(マネー)を全身の血管に送る心臓の機能を論じるようなことです。【プレミアム読者アンケート&感想の、項目のメド】
1.内容は、興味がもてますか?
2.理解は、進みましたか?
3.疑問な点は、ありますか?
4.その他、感想、希望テーマ等
5.差し支えない範囲で、横顔情報があると、テーマ設定と記述の際的確に書くための、参考になります。
気軽に送信してください。感想は、励みと参考になり、うれしく読んでいます。質問やご要望には、可能なかぎり回答をするか、あとの記事・論考に反映させるよう努めます。
読者の感想・意見・疑問・質問は、考えを広げるのに役立ちます。
著者のメールアドレス:yoshida@cool-knowledge.com本ウェブマガジンに対するご意見、ご感想は、このメールアドレス宛てにお送りください。
配信記事は、マイページから閲覧、再送することができます。
マイページ:https://foomii.com/mypage/
【ディスクレーマー】
ウェブマガジンは法律上の著作物であり、著作権法によって保護されています。
本著作物を無断で使用すること(複写、複製、転載、再販売など)は法律上禁じられています。
■ サービスの利用方法や購読料の請求に関するお問い合わせはこちら
https://letter.foomii.com/forms/contact/
■ よくあるご質問(ヘルプ)
https://foomii.com/information/help
■ 配信停止はこちらから:https://foomii.com/mypage/