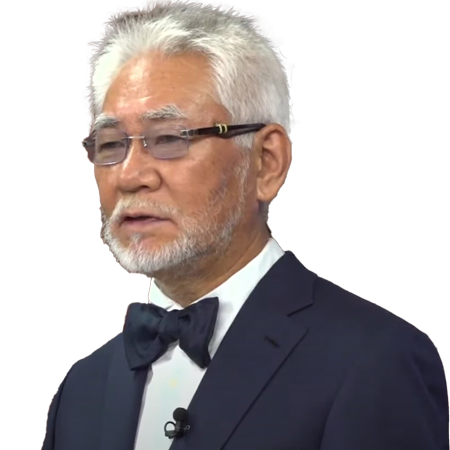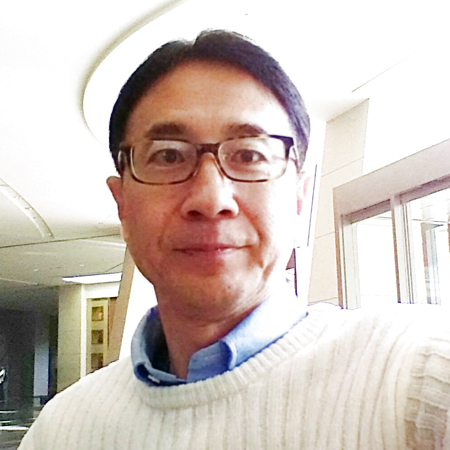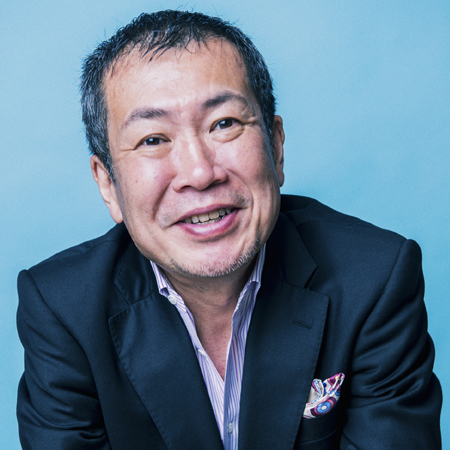… … …(記事全文3,732文字)過剰生産の背景に党幹部の利権動機
共産党主導経済では、企業がどんどんモノを作れば、党幹部にほめられるという悪しき習慣がある。生産量を増やせば、幹部のフトコロに入る利権が増えるからである。
赤字操業の国営企業が生産を縮小して従業員を解雇したくても、企業を仕切る共産党幹部の責任が問われてしまうので、ズルズルと現状容認になってしまう。大手国営企業ともなると、共産党幹部が国家の政治権力と直接結びついた中央委員だったりするので、リストラなどなかなかできない構造になっている。
歴史的に見てみよう。
胡錦濤政権時代、8%の経済成長率を死守するという「保八(ル ほはち)」が唱えられた。これは、党官僚が官営事業による収入の8%を己の利権とする慣行が背景にある。中国経済成長率というのは、その年の3月に開かれる全国人民代表大会(全人代、共産党主導の国会で年に一度開催)で政府目標として公表される数値が通常の場合は達成されることになっている。この目標値なるものは、前年秋の党中央経済工作会議で決められる。この目標値に沿って国有企業、中央政府、地方政府及び政府機関の資金計画や予算が決まる。つまり8%の経済成長が達成されないと、党官僚は権益を確保できなくなるのだ。
しかし、習近平が党総書記として実権を握った2012年は当局発表の実質成長率が7.9%と8%ラインを切り、国家主席に就任した翌年の習政権時代到来とともに「保八」は終わった。
これは、「おこぼれの構造」がどんどん細っていくことを意味する。新卒の学生や農村の余剰人員による工場労働者(農民工)など、新規の労働力を吸収するためにも8%成長は必要だったのだが、成長率が8%を切ると、既存の労働者を雇いつづけるのがやっとという現状では、それもできない。そうして失業者が増えれば、政府への不平不満が鬱積して社会不安につながる。成長率が8%台を切った頃から民衆暴動が年間30万件も起きた。習政権はそうした不穏な情報は一切、隠蔽しているので暴動件数は不明なままだ。